今、補助金と合わせて助成金の活用が、中小企業では外せないキーワードではないでしょうか。
私も、数多くの中小企業を訪問する中で、助成金の活用に関する相談を数多く受けてきました。
補助金と比較すると金額が少ないため、助成金の受給を重要視していない方も多くいらっしゃるかもしれませんが、雑収入として計上される助成金は、利益率から計算すると売り上げベースでは決して侮れる数字ではありません。
しかし、当然どの企業でも簡単に受給できるわけではなく、数多くの条件が存在しているなどハードルがいくつか存在しています。
そのハードルの一つは、どんな助成金があり、どの助成金が自社の取り組みに合致しているのかを把握することです。
そこで今回は、助成金を受給するために必要なポイントをまとめました。この記事を参考にてしっかりと助成金を受給していってください。
助成金受給に逃せない5つのポイント
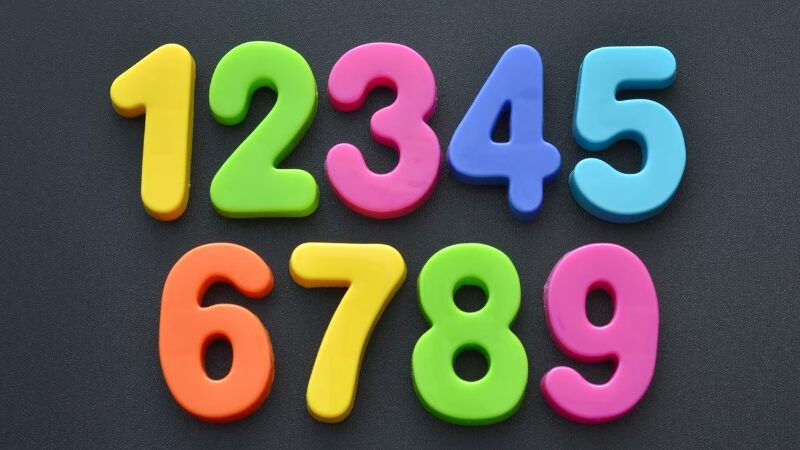
自社に合った助成金を選ぶこと
助成金は種類が多く、それぞれ支給対象や条件、使い道が異なります。自社に合わない助成金を選ぶと、申請書類の準備や制度導入に時間や手間がかかる割に、結局要件を満たせず不支給になるリスクが高くなります。
たとえば、雇用関係の助成金は正社員の採用や就業規則の見直しが必須ですが、事業規模や現状の体制によっては制度対応が難しい場合もあります。また、対象となる事業内容や地域、業種が限定されているケースも多いです。
限られた人員でバックオフィスを兼務している中小企業にとって、無駄な申請作業は大きな負担になります。自社の現状や今後の方針にマッチした助成金を選ぶことで、申請の負担を減らし、確実に受給につなげることができます。
申請条件・要件を正確に確認すること
助成金はそれぞれ細かな申請条件や要件が定められており、少しでも条件を満たしていないと申請が通らない、もしくは受給後に返還を求められるケースもあります。
たとえば「申請時点で従業員を○人以上雇用していること」「新たな制度導入を○日までに完了していること」「過去に同様の助成金を受けていないこと」など、見落としがちなポイントも多く、実際に申請直前や審査時に発覚して受給できなかった事例も珍しくありません。また、助成金によっては「申請前に事業を開始してしまうと対象外」などタイミングも非常に重要です。
条件や要件を正確に理解していないと、せっかく準備しても労力が無駄になるだけでなく、会社の信頼にも影響します。そのため、募集要項やガイドラインをしっかり確認し、自社が本当に要件を満たしているか事前に確認することが、受給への確実な第一歩です。
スケジュール管理を徹底すること
助成金の申請には、募集開始から締切までの期間が厳格に設定されていることが多く、スケジュール管理を怠ると申請そのものができなくなります。
また、多くの助成金では「申請前に事業を開始した場合は対象外」など、タイミングに関する条件が細かく定められています。さらに、必要書類の収集や作成、社内の制度改定など準備に時間がかかる場合も多いため、ギリギリに動き始めると不備やミスが発生しやすく、結果として不支給となるリスクが高まります。
中小企業は限られた人員で業務を回しているケースが多く、他の業務と並行して助成金申請の準備を進める必要があるため、タスクや期限を見える化し、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。早め早めの行動が、助成金受給の確率を大きく高めます。
必要書類・証拠書類を揃えること
助成金申請では、事業計画書や見積書、就業規則、労働契約書、給与明細、タイムカードなど、多くの書類や証拠資料の提出が求められます。これらは助成金の要件を満たしているか、実態が適切かを審査するための重要な判断材料となります。書類の不備や不足があると、申請自体が受理されなかったり、追加提出や修正を求められることで手続きが遅れ、最悪の場合は不支給となるリスクもあります。
特に中小企業では、日常業務の合間にこれらの書類を準備するのは負担が大きいため、早めにリストアップして整理することが不可欠です。また、証拠書類の保存期間やフォーマットにも注意が必要です。しっかりとした書類管理が、スムーズな申請と確実な受給につながります。
専門家や支援機関を積極的に活用すること
助成金の申請手続きは複雑で、条件や必要書類、申請方法も助成金ごとに異なります。初めて申請する場合や、担当者が他の業務と兼任している中小企業では、見落としやミスが起きやすく、不支給や申請手続きのやり直しになるリスクも高まります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、社会保険労務士や行政書士、商工会議所などの支援機関を早い段階から活用することが重要です。専門家は最新の制度情報や実務経験が豊富で、要件確認や書類作成のアドバイス、申請サポートまできめ細かく対応してくれます。
助成金の活用事例や審査ポイントも知っているため、自社だけで申請するより受給の可能性が大きく高まります。分からないことは早めに相談し、専門家の知見を最大限に活かすことが、スムーズな受給への近道です。
助成金受給時の注意点

虚偽申請やごまかしを絶対にしないこと
助成金申請において虚偽の内容を記載したり、事実と異なる書類を提出することは、たとえ小さなごまかしであっても絶対に避けるべき重大なリスク行為です。もし虚偽申請が発覚した場合、受給した助成金は全額返還を求められるだけでなく、加算金や違約金、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。また、悪質なケースでは企業名が公表され、社会的信用や取引先との信頼関係にも大きなダメージを受けかねません。
助成金の審査は年々厳格になっており、申請内容のチェックだけでなく、受給後の現地調査や証拠書類の追加提出が求められることも増えています。例えば、実際には雇用していないのに雇用実績を水増ししたり、使用していない設備投資を申請内容に含めた場合、後から証拠の提出や現地確認を求められた際に矛盾が明らかになります。その時点で虚偽が判明すれば、今後の助成金申請ができなくなるだけでなく、経営者自身にも責任が及ぶ恐れがあります。
中小企業にとって助成金は貴重な経営資源ですが、信頼を損なうことは企業の存続に関わる深刻なリスクです。短期的な利益や手間の軽減を優先せず、常に正直・誠実な対応を徹底することが、企業の成長と信用を守るために何より重要です。
受給後も必要な報告や書類保存を忘れないこと
助成金を受給した後も、必要な報告や書類保存をきちんと行うことは非常に重要です。助成金の多くは、受給後も一定期間にわたり事業の実施状況や経費の使途などを報告する義務があり、行政機関や審査機関から追加の証拠書類の提出や実地調査を求められることがあります。もし、報告を怠ったり、証拠となる書類を紛失・破棄してしまった場合、最悪の場合は受給した助成金の返還や、今後の助成金申請の停止措置を受けるリスクがあります。
また、助成金によっては、報告や書類の保存期間が定められていることも多く、受給後数年間は原本を保管しなければなりません。これを守らないと、「適正な支出が証明できない」と判断され、不正受給と見なされるケースもあります。特に中小企業では、日々の業務が忙しく、助成金に関する事務処理が後回しになりがちですが、きちんと管理体制を整えておくことが大切です。
助成金は受給して終わりではなく、適切に管理・報告することまでが一連の流れです。信頼を損なわないためにも、受給後の対応を怠らず、正確な記録と報告を心がけましょう。
申請前に必ず最新の募集要項やガイドラインを確認すること
助成金は毎年制度内容や申請要件、提出書類、募集期間などが変更されることが多く、前年や過去の情報をもとに準備を進めてしまうと、思わぬミスや漏れが発生する危険があります。例えば、申請対象となる事業内容や設備投資の範囲が変更されていたり、従業員数や雇用条件などの細かな要件が追加・削除されていることも珍しくありません。また、必要となる証拠書類や申請書式が毎年アップデートされている場合もあり、古いフォーマットで提出したために申請が受理されなかったり、追加提出を求められるケースもあります。
さらに、申請スケジュールや締切日、提出方法(オンライン申請への移行など)が変更されていることもあるため、古い情報のまま動いてしまうと、せっかくの準備が無駄になるだけでなく、申請自体ができないリスクも高まります。特に中小企業は限られた人員で申請業務を行うため、事前に最新の募集要項やガイドラインを細かくチェックし、必要な情報をしっかり整理しておくことが不可欠です。
最新情報を確認することは、無駄な手間やリスクを回避し、確実に助成金を受給するための基本中の基本です。
まとめ
今回は助成金受給のための重要ポイントと注意点をまとめていきました。
雇用保険を原資として支給される助成金は、知っている会社が得をして、知らない会社は損をし続けます。
しっかりとした準備をして、毎年安定した助成金受給を目指しましょう。
またこの他の記事では、おすすめの補助金や、補助金受給のためのポイントなどもまとめています。併せて参考にしてください。
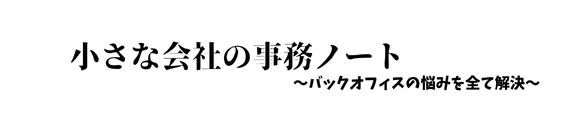
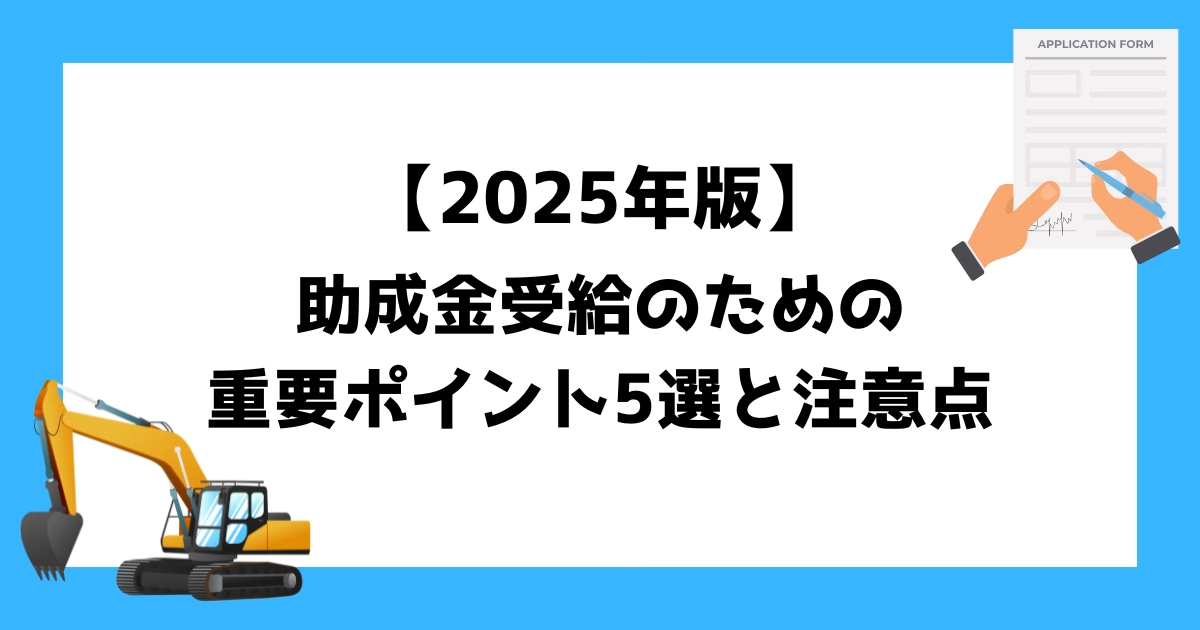

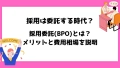
コメント