中小企業にとって助成金は「返済不要」で使える大切な資金源です。とはいえ数が多く、どれが自分たちに合うのか分かりづらいのも事実。
そこで本記事では、中小企業がよく活用している定番助成金6種類をまとめました。さらに「結局どれから申請すべき?」という疑問に答えるため、最後におすすめベスト3も紹介します。
キャリアアップ助成金
概要
有期雇用やパート・アルバイトを、正社員や無期雇用に転換したときに受けられる助成金。人材定着に直結する定番です。
支給額
- 有期→正社員:57万円/人(中小企業の場合)
- 有期→無期雇用:28.5万円/人
- 生産性要件クリアで加算(+9.5万円/人)
要件
- 就業規則に転換制度を整備していること
- 6か月以上継続勤務している有期社員を対象にすること
- 転換後に基本給を5%以上アップすること
申請流れ
- 事前に「キャリアアップ計画」を提出
- 正社員転換を実施
- 6か月以上継続勤務を確認
- 支給申請
注意点
- 事前計画を出していないと対象外
- タイムカード・賃金台帳など証拠書類が揃っていないと不支給
トライアル雇用助成金
概要
就職に不利な状況にある人を「お試し雇用(原則3か月)」した場合に受給できる助成金。採用のミスマッチを防ぎやすい。
支給額
- 4万円/人・月 × 最長3か月 → 最大12万円
要件
- ハローワークや職業紹介事業所の紹介経由で採用
- 原則3か月以内の有期雇用契約を結ぶこと
- 雇用管理上の問題がないこと
申請流れ
- ハローワークにトライアル雇用求人を提出
- 対象者を雇用・契約
- トライアル期間終了後に支給申請
注意点
- ハローワーク経由以外の採用は対象外
- 本採用につながらないと、次の助成金支給に不利になることも
働き方改革推進支援助成金
概要
残業削減や労務管理改善のために就業規則改定やシステム導入をした場合に使える助成金。
支給額
- 費用の3/4(上限200万円)を助成
- 対象:労務管理システム、勤怠打刻機器、就業規則作成など
要件
- 36協定を結び、時間外労働削減の計画を立てていること
- 実際に残業削減や勤務間インターバル導入などを実施すること
申請流れ
- 事前に計画書を提出
- システム導入や規則改定を実施
- 実績報告を提出し、支給申請
注意点
- 必ず取組前に申請すること
- 年度予算に限りがあり、申請枠が埋まると早期終了
両立支援等助成金
概要
社員が育児や介護と仕事を両立できるよう制度を整え、実際に利用した場合に支給される助成金。
支給額
- 育休復帰支援コース:57万円/人
- 介護離職防止コース:最大72万円/人
- 両立環境整備コース:上限50万円
要件
- 就業規則で両立支援制度を整えていること
- 実際に育休・介護休業を取得し、復職していること
- 必要書類(就業規則・休業申出書・復帰証明など)が揃っていること
申請流れ
- 制度整備と事前申請
- 育休や介護休業を実施
- 復職確認
- 支給申請
注意点
- 実際に利用者が出ないと対象外
- 書類不備や復職確認が取れないと不支給
人材開発支援助成金
概要
社員の研修や資格取得などスキルアップに使える助成金。
支給額
- 賃金助成:960円/時間・人(最大1,200円)
- 経費助成:45%(最大60%)
- ITやデジタル分野などの特定訓練は加算あり
要件
- 訓練計画を作り、事前に届け出ること
- 厚労省が認める訓練であること(外部研修だけでなく社内研修も可)
- 訓練中も労働者に賃金を支払うこと
申請流れ
- 訓練計画提出
- 訓練を実施
- 実績報告・支給申請
注意点
- 通常業務とみなされる内容は対象外
- 研修時間の出勤簿やタイムカード記録が必要
業務改善助成金
概要
最低賃金を一定額引き上げ、あわせて業務効率化のための設備投資をした場合に受けられる助成金。
支給額
- 設備投資費用の3/4(上限600万円)
- 投資例:PC更新、POSレジ、自動釣銭機、システム導入など
要件
- 地域別最低賃金を一定額以上引き上げること
- 設備投資を同時に実施すること
- 賃金引上げ計画を提出していること
申請流れ
- 賃金引上げ計画を提出
- 設備投資を実施
- 実績報告・支給申請
注意点
- 賃上げが伴わなければ対象外
- 予算枠が限られており、毎年早期終了しがち
おすすめの助成金ベスト3

第1位:キャリアアップ助成金
→ 非正規から正社員化はどの業種でもニーズが高く、金額も大きい。定着率UPにも直結。
第2位:業務改善助成金
→ 賃上げと設備投資をセットで支援。効率化の実感が出やすく、補助率も高い。
第3位:人材開発支援助成金
→ 社員教育に使いやすく、IT・デジタル研修の加算で今の時代に合う。
助成金活用の注意点 3つ
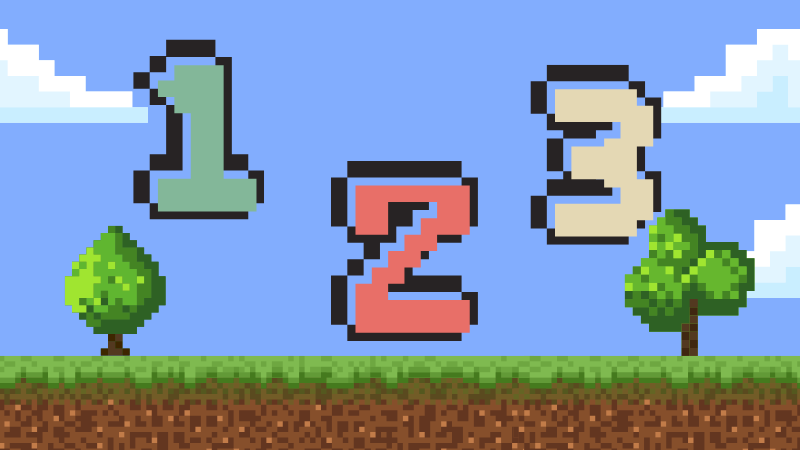
事前申請が必須
助成金活用で最も大きな落とし穴の一つが「事前申請を出していないために不支給になる」というケースです。多くの助成金は「取り組みを始める前に計画を提出すること」が条件になっています。
たとえばキャリアアップ助成金であれば、非正規社員を正社員に転換する前に「キャリアアップ計画書」を労働局へ届け出なければなりません。逆に言えば、すでに転換してしまった後で「申請できそうだから」と思っても、その時点では対象外になってしまうのです。これは制度の性質上、国として「事前に計画を立てた企業を支援する」ことを目的にしているためです。
中小企業では日常業務が忙しく、つい「終わってから申請できるだろう」と後回しにしがちですが、助成金に関してはそれが致命的なミスになります。対応策としては、新しい雇用や制度変更を検討した段階で、必ず社労士や労働局に確認し、計画書を先に提出しておくことです。これを習慣化するだけで、せっかくのチャンスを逃さずに済みます。
証拠書類の保存が必須
助成金を受け取る際に意外と見落とされがちなのが「証拠書類の保存」です。助成金は単に「やった」という事実だけでは支給されず、「本当に実施したことを裏付ける書類」が揃っているかどうかで判断されます。たとえばキャリアアップ助成金であれば、正社員化したことを示す雇用契約書、転換前後の賃金台帳や出勤簿が必要です。人材開発支援助成金なら、研修時間を確認できる出勤簿や受講記録、講師への支払い領収書が求められます。
中小企業では「普段の管理は口頭やエクセルで十分」と考える場面も多いですが、助成金の審査では形式が厳格にチェックされます。領収書が紛失していた、タイムカードに記録がない、契約更新時の書類が保管されていない──こうした小さな抜けが理由で不支給になることも少なくありません。
対策としては、取り組みを始める段階で「どの書類を残せばいいか」を把握し、専用フォルダやキャビネットに一括管理しておくことです。証拠書類を整えるのは事後では間に合わないことが多いため、準備と同時に証拠を残す習慣を持つことが、助成金活用を成功させる第一歩になります。
予算枠・期限がある
助成金には必ず「予算枠」と「申請期限」が設けられています。国の助成金は年度ごとの予算で運用されるため、人気の高い制度は早期に受付終了してしまうことも珍しくありません。たとえば業務改善助成金は、設備投資を伴うことから申請件数が多く、例年早い段階で予算が消化され「受付終了」となるケースが見られます。
また、期限の管理も重要です。「取り組みが終わってから〇か月以内に申請」という制約がほとんどで、1日でも遅れると不支給になる場合があります。日々の業務に追われて申請が後回しになり、「せっかく条件を満たしているのに申請できなかった」という中小企業も少なくありません。
対策としては、制度情報をこまめに確認し、計画段階からスケジュールに「申請期限」を組み込んでおくことです。さらに、早めに労働局や専門家へ相談して申請書類を整えておけば、予算打ち切りや期限切れで取りこぼすリスクを最小限にできます。助成金は「早めに動いた企業ほど取りやすい」制度であることを忘れないことが大切です。
まとめ
助成金は「知っているかどうか」で受給できるかが決まります。6つの定番を把握しておけば、自社で狙えるものがすぐ分かるはずです。
まずは キャリアアップ助成金・業務改善助成金・人材開発支援助成金 の3つから検討すると取り組みやすいでしょう。
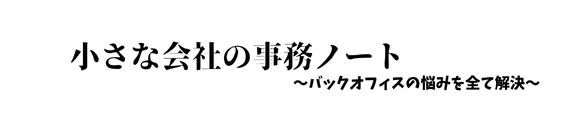
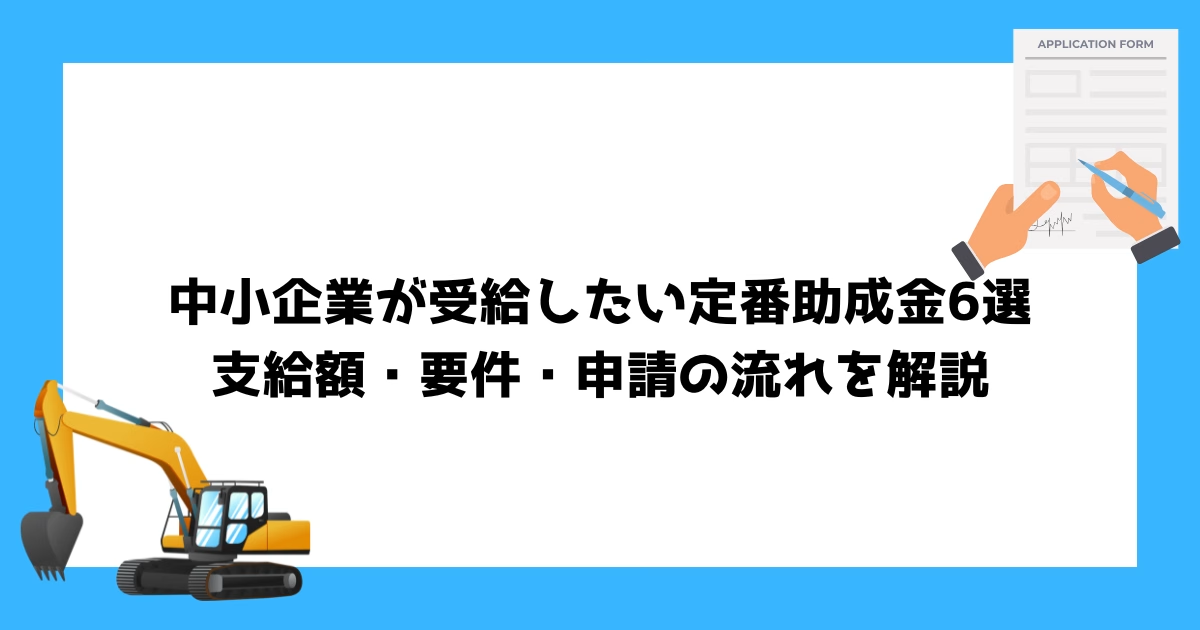

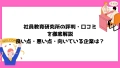
コメント