創業したての方、これから創業予定の方は「どの金融機関に相談すればいいのか…」と迷われているのではないでしょうか。
銀行、信用金庫(信金)、信用組合(信組)名前は知っていても、違いや特徴、実際に創業期に相談しやすいのはどこなのか、いまいちピンと来ない方も多いはずです。「メガバンクは厳しいって聞くけど、信用金庫や信用組合って実際どうなの?」「融資が出やすいのは?」「親身に相談に乗ってくれるのは?」など、最初の一歩でつまずくケースも珍しくありません。
この記事では、創業直後やこれから開業する方向けに、【銀行・信金・信組の違い】と、どの金融機関にまず相談すれば良いかを、実際の現場での違いや特徴をもとに分かりやすく解説します。
迷わず、失敗せず、自分に合った金融機関選びができるよう、ぜひ参考にしてみてください。
金融機関としての規模感

金融機関の規模や営業エリアの違いは、創業者にとって重要なポイントです。全国展開している巨大銀行なのか、地域限定で営業する地元密着型なのかによって、利用者に提供されるネットワークやサービスの範囲が異なります。それぞれの規模感の特徴を整理します。
メガバンク(都市銀行)
三菱UFJ・三井住友・みずほ(+りそな)のような全国規模(海外支店も保有)の巨大銀行です。全国どこでも支店網・ATM網を利用できる利便性や、銀行の信用力の高さによる社会的信頼というメリットがあります。
取引企業の業種や所在地を問わず幅広く対応でき、将来的に事業を全国・海外展開する可能性がある場合にはメガバンクとの取引が視野に入ります。ただし、その一方で中小企業にとっては組織が大きすぎて声が届きにくい面があります。創業当初から全国対応のネットワークが必要なケースは稀であり、まずは地元での実績作りが優先となるでしょう。またメガバンクは優良大口顧客に経営資源を振り向けるため、規模の小さな企業一社あたりに割けるサービスは限定的です。
総じて、規模のメリットは大きいものの、小規模企業に対してはスケールが合わない部分があると言えます。
地方銀行(地銀)
各地域(都道府県)に本拠を置き、その地域経済を主な営業範囲とする銀行です。例えば○○銀行(県名や地域名が入る)という名称が付いているのが特徴です。店舗網は本店のある都道府県内が中心で、地元の有力企業のメインバンクとなっているケースが多く見られます。
地方銀行は地域経済との結びつきが強く、自治体や地元企業とのネットワークに優れます。そのため地域の情報や商習慣に詳しく、地元ならではのきめ細かな対応が可能です。営業エリアは全国ではありませんが、近年では地銀同士の広域連携や統合も進んでおり、複数県にまたがる地盤を持つ銀行も出てきています(例:○○フィナンシャルグループ傘下の銀行など)。
全国対応力ではメガバンクに劣るものの、「地元密着」で企業を支える存在として、地場の中堅・中小企業には欠かせない存在です。
信用金庫(信金)
特定地域に根差した協同組織金融機関で、その地域の中小企業・住民が会員(出資者)となって運営に参加しています。営業エリアは各信金ごとに定められており、原則として本拠地のある市町村やその周辺地域に限られます。たとえば東京の信用金庫なら23区東部、といった具合に担当エリアが細かく分かれています。
規模としては預金・貸出金残高で見ると地方銀行より小さく、支店数も地域内に限られます。しかしその分、地域密着型で小回りがきくのが強みです。地域の企業・住民との距離が近く、「街のかかりつけ銀行」として細やかなサービス提供を行っています。また非営利組織であることから営利目的の制約が少なく、地域貢献的な事業にも積極的です。信用金庫は中小企業・個人事業主を主要顧客としているため、創業期~年商数億円規模までの企業にとって適したスケール感と言えます。反面、扱える業務範囲は地元に限定され、大企業向けの大型融資や海外取引などは不得手です。
「地域限定だが密着度が高い」のが信用金庫の規模的特徴です。
信用組合(信組)
信金と同様に地域限定の協同組織金融機関ですが、さらに対象地域・業種が限定されている点で異なります。例えば〇〇信用組合は△△県内の農業従事者、□□信用組合は○○市内の中小商工業者、といった具合に組合ごとに加入資格(地区や職域など)が定められています。そのため、自社がその組合の対象に該当しない場合は利用できません。一方で対象に当てはまれば組合員として迎え入れられ、内部のネットワークや業界特有の情報など組合ならではのメリットを享受できます。
信用組合の規模は信金よりもさらに小さく、店舗は本店+数支店のみというケースも多いですが、その分経営者との距離は極めて近いです。「地域・業界の駆け込み寺」として、狭い範囲に深く根を張った活動をしています。
総じて、信用組合は極小規模・ニッチ分野に特化したスケール感の金融機関と言え、会員となる小規模事業者にとっては頼れる存在です。
融資の出やすさ
創業時に資金を借りやすいかどうかは金融機関の種類によって大きく異なります。一般に「金利が高い金融機関ほど審査が緩く、金利が低い金融機関ほど審査が厳しい」という傾向があります。これは貸し倒れリスクと金利水準がトレードオフの関係にあるためです。
実績の少ない創業フェーズでは、多少金利が高くても借りやすい金融機関を利用することが現実的です。各種金融機関の創業融資に対する姿勢の違いは次のとおりです。
メガバンク
国内最大級の金融機関で資金力があり金利も低めですが、融資審査は非常に厳格です。
年間売上10億円以上の中堅・大企業を主な対象としており、少額の融資案件や創業間もない小規模企業への融資には消極的です。創業期の中小企業は融資の優先度が低く、実際に創業融資の件数ランキングでもメガバンクはトップ10に一行も入っていない状況です。
審査基準の厳しさから、信用保証協会付きの融資であっても門前払いとなるケースが多く、創業当初にメガバンクから直接融資を引き出すのは極めて難しいと言えます。
地方銀行
本店のある都道府県を中心に展開する地域密着型の銀行です。メガバンクと同じ銀行法に基づく営利企業ですが、地元中堅企業との取引に積極的で、信用保証協会付き融資を中心に数百万円規模の小口融資にも対応してくれます。そのため地方の中小企業や個人事業主の資金調達を支える重要な役割を担っています。
ただし、融資判断はやや保守的で、基本的には保証協会付き融資から取引を始めるケースが多く、無保証のプロパー融資には積極的ではありません。プロパー融資を行う場合でもメガバンクより金利が高めに設定される傾向があります。
つまり地銀は「保証付きなら柔軟だが、直接融資は慎重」という姿勢です。また、地方銀行は信用金庫より金利が低く融資可能額も大きい分、審査ハードルは信用金庫より厳しめになっています。創業融資に積極的な地銀も存在しますが、銀行によって姿勢に差がある点には注意が必要です。
信用金庫
地域に根差した非営利の協同組織金融機関です。会員である地元の中小企業・個人事業主の相互扶助・地域繁栄を目的としており、営業エリア内の企業や個人しか利用できません。取引対象は比較的小規模の事業者が中心で、基本的に創業融資に積極的です。営利第一ではなく地元支援を重視するため、中小企業や個人事業主にも前向きに融資してくれる傾向があります。
実際、創業融資の件数でも信用金庫は常に上位に位置し、多摩信用金庫(東京都)などは全国トップクラスの実績を持ちます。審査も地元企業の将来性を評価する柔軟性があり、創業時でも融資が通りやすい金融機関と言えます。
ただし、信用金庫は一件あたりの融資額が小口(融資額の中心は1,000万~3,000万円程度)となりがちで、それ以上の規模の資金需要には単独では対応が難しくなる場合があります。また、金利は都市銀行より約1%高く、地方銀行より0.5%ほど高めに設定されるケースが多く、事務コスト等を賄う必要があるためです。それでも「借りやすさ」の面では都市銀行・地銀より勝り、審査ハードルは比較的低いとされています。
信用組合
信金と同じく非営利の協同組織金融機関で、さらに規模が小さい極めて地域密着型の金融機関です。会員制で特定地域や特定業種の組合員を対象とすることが多く、自分の会社が対象地域・業種に該当する場合に利用できます。対象となる業種であれば創業融資にも柔軟に対応してくれるなど、小規模事業者に親身な融資姿勢を持ちます。
信用金庫と同様に信用保証協会付き融資が基本で、小口融資を数多く扱うため審査基準は比較的緩やかです。その反面、利用には会員資格が必要でエリアや業種が限定される点と、組織自体の規模が小さいため扱える融資額やサービス範囲に限界がある点がデメリットです。とはいえ、該当する地域・業界の創業者にとっては最も身近で相談しやすい金融機関の一つです。
なお、信用金庫・信用組合とも近年は地域経済の活性化のため保証なしのプロパー融資にも積極的に取り組む動きが増えてきています。プロパー融資の場合、金利は高めになる傾向がありますが審査は柔軟で、担保や保証人に頼らず融資を受けられる可能性が広がっています。
相談体制

金融機関ごとに、創業予定者に対する相談対応の手厚さや担当者との距離感にも違いがあります。規模が小さい金融機関ほど経営者との接点が密で「親身」な対応が期待でき、大規模な銀行ほど事務的・画一的な対応になりがちです。その違いを見てみましょう。
メガバンク
総合力では優れるものの、創業期の小規模企業に対しては相談窓口のハードルが高いのが実情です。
メガバンクは顧客企業を信用格付けなどでランク管理しており、融資残高が少ない零細企業や財務内容が脆弱な企業は担当者の定期訪問の対象外となってしまいます。創業前後の企業には専任の営業担当者が付かない場合も多く、こちらから出向いて相談しようとしても「まずは実績を作ってから」という対応をされるケースが少なくありません。
したがって親身な創業相談や経営支援をメガバンクに期待するのは難しいでしょう。もっとも、大企業向けには専門部署でコンサルティング機能も持っていますが、創業フェーズの企業との距離感は遠い傾向にあります。
地方銀行
地域に根差した銀行であり、地元企業の発展が自行の成長にも繋がるため中小企業への経営支援にも一定の関心を持っています。
創業支援に積極的な地銀の場合、創業セミナーや創業相談会を開催するなど情報提供に熱心で、創業予定者が相談しやすい体制を整えているところもあります。こうした銀行では専門の創業支援デスクや担当者が親身に話を聞いてくれるでしょう。ただ一方で、創業融資に消極的な地銀も存在し、その場合は相談対応も形式的なものに留まる可能性があります。地方銀行全般として言えるのは、メガバンクほどドライではないものの、信用金庫ほど密着した関係ではないという中間的な立ち位置です。
初回取引では保証協会付き融資から始め、返済実績を積んでから徐々に深い相談相手になっていくケースが多いです。したがって、創業時に地銀を利用する場合は「創業支援に力を入れている銀行かどうか」を見極めることが大切です。
信用金庫
「フェイス・トゥ・フェイス」を掲げる信用金庫は、経営者との距離が近く定期的な訪問や対話を重視しています。
得意先係(担当者)が毎月会社を訪問し、月次試算表や資金繰り状況の相談に乗ってくれるなど、創業間もない企業にも非常に親身です。融資の大小に関わらず、一社一社に丁寧に対応してくれるため、「困ったときはまず信金に相談」という中小企業経営者も多くいます。また信用金庫は融資だけでなく経営相談やビジネスマッチングなど融資以外の支援にも積極的で、創業者にとって心強い存在です。担当者との距離感が近いため、事業計画のブラッシュアップや各種支援制度の活用についてアドバイスをもらえるケースもあります。
要するに、創業期に最も「伴走型」で寄り添ってくれる金融機関が信用金庫だと言えます。
信用組合
信用組合も信用金庫と同様に地域密着型で、規模が小さい分フットワークの軽い対応が期待できます。
組合員同士のネットワークもあり、業界特化型の信組ではその業界事情に精通した担当者が相談に乗ってくれることも強みです。「組合員の相互扶助」という建前から、小規模事業者の話を親身に聞いてくれる姿勢は信用金庫以上に強い場合もあります。ただし、信用組合自体の人員や店舗網が限られるため提供できるサービスは地域内で完結するものが中心です。また会員制ゆえに自社が対象地域・業種に入らないと取引できない点には注意が必要です。
しかし該当する場合には、身近な頼れる創業サポーターとして活用できるでしょう。
会社規模別のおすすめ先
最後に、企業の規模(ステージ)に応じて、どのタイプの金融機関が向いているかを整理します。創業前~創業直後の段階と、従業員数や売上規模が大きくなった段階では、適切な金融機関の選択肢も変わってきます。特に「どこに最初に相談すべきか」という点を念頭に、規模別のおすすめを解説します。
個人事業主・創業準備中(創業前)
まだ法人化しておらず従業員もいないか、ごく少人数で事業計画を温めている段階では、まず地域の信用金庫や信用組合を最初の相談相手に選ぶのがおすすめです。信用金庫・信組は創業融資の実績が豊富で、事業計画のブラッシュアップや創業計画書の作成アドバイスなどにも親身に対応してくれます。特に信用金庫は中小企業・個人事業主の創業融資に積極的で、「創業融資の入り口」として最適な存在です。
一方、メガバンクにこの段階で相談しても厳しい審査基準で門前払いとなり時間をロスする可能性が高いため、現実的ではありません。地方銀行については、地元で創業支援に積極的な地銀があれば検討してみる価値があります。積極的な地銀は創業者向けの融資商品や保証協会と連携した制度融資を用意しており、信用金庫と並んで創業時の資金調達先になり得ます。
なお、民間銀行ではありませんが政府系金融機関の日本政策金融公庫(日本公庫)も創業者向け融資制度が非常に充実しています。公庫は無担保・無保証人での低利融資枠(新創業融資など)を提供しており、創業時に多く利用されます。実際、創業前後の資金調達では「日本公庫+信用金庫(または信用組合)」の二本柱でスタートするケースが一般的です。
公庫で資金を借りつつ、返済口座を置く信用金庫・地銀をメインバンク候補として関係を築いていくと良いでしょう。
数人規模の創業企業(創業直後~創業数年以内)
創業して間もなく、社員が数名程度まで増えてきた段階では、引き続き信用金庫がメインバンクとして非常に頼りになります。信用金庫はこの規模の小規模企業を主要顧客としているため、創業後の運転資金のやりくりから設備資金まで相談に乗ってくれます。融資面では信用保証協会付きで数百万円~数千万円規模までの融資に対応可能であり、創業後の成長を支える身近な資金供給源となります。また担当者が継続して会社の状況を見守ってくれるため、業績が芳しくないときでもリスケジュール(返済猶予)等の相談がしやすいのも信金ならではの強みです。
一方、事業が軌道に乗り始めて融資ニーズが数千万円規模に達しそうな場合には、地方銀行の活用も視野に入れます。地銀は信用金庫より大口の融資余力があり、設備投資など中期的な資金需要にも応えられるため、必要に応じて信金と地銀の両方から融資を受ける体制を整えることもあります。
この時期はまだ年商規模で数千万円~1億円未満程度でしょうから、メガバンクは取引対象になりにくいですが、信金・信組+地銀で融資の幅を広げていく時期と考えるとよいでしょう。
従業員10名以上のスタートアップ(成長拡大期)
社員が二桁に達し、本格的に事業拡大を図る段階では、売上規模も数億円規模に近づいている可能性があります。このフェーズでは、引き続き地元の信用金庫と良好な関係を維持しつつ、地方銀行との取引を本格化させることが多いです。地銀は年商1億~10億円規模の地域中堅企業を主要顧客としているため、10名前後の成長企業であれば本格的に相手をしてくれるようになります。地銀からより大きな融資枠(例えば数千万円~1億円超)を確保し、信用金庫では日常の決済や小口融資を引き続き利用するといった形で、それぞれの強みを活かすと良いでしょう。
さらに、会社の年商が数億円を超えてくるようならメガバンクや商工中金などとも取引を開始するタイミングです。目安として年商3億円以上になれば、商工中金(政府系の中小企業専門金融機関)やメガバンクが新たな融資先候補に入ってきます。この段階では信用保証協会付き融資から保証の付かないプロパー融資へ移行していくことが理想とされます。
メガバンクは一般に年商10億円以上を主要なターゲットとするため、10名規模のスタートアップではまだ取引対象とならない場合もあります。ただし、ベンチャー企業など成長スピードが速い会社ではメガバンクのベンチャー支援部門やグループのベンチャーファンド等から声が掛かるケースもあり、将来の大型融資に向けて関係構築を始めることもあります。いずれにせよ、事業規模の拡大に応じてメインバンクを信金→地銀→メガバンクへと段階的に展開していく戦略が有効です。
まとめ
創業時の金融機関選びは、今後の事業運営を大きく左右する大事な一歩です。メガバンク・地方銀行・信用金庫・信用組合、それぞれに強みやサポート体制、融資のハードルの違いがありますが、「事業の規模」「エリア」「相談のしやすさ」を踏まえて選ぶことで、無理なくスムーズな資金調達や経営相談が実現できます。
迷ったら、まずは創業支援に積極的な信用金庫や信用組合、地域の地方銀行など話しやすい金融機関からスタートするのがおすすめです。必要に応じて複数行と面談し、自分に合った金融機関を見つけてください。
金融機関との良好な関係づくりは、創業後も事業を支える大きな武器になります。焦らず一歩ずつ、自分らしい創業のスタートを切りましょう。
また、他の記事では決算書の見方や資金繰り表テンプレートについても詳しくまとめています。併せて参考にしてみてください。
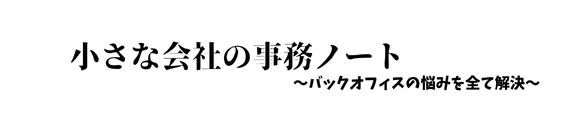
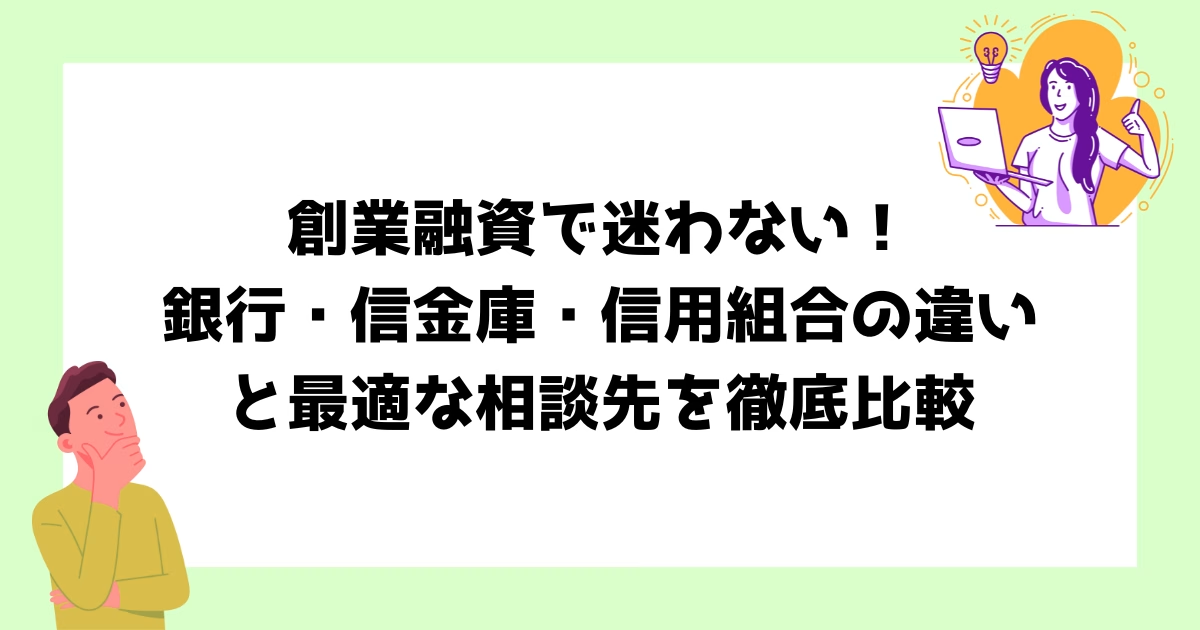
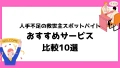
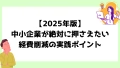
コメント