中小企業でも賃上げは実現できる!結論と今すぐやるべきポイント
最初に結論からお伝えすると、賃上げ実現のために今すぐに取り組むべきことは以下の3つです。
- 「賃上げ原資」は“経費の見直し”と“助成金活用”でつくる
- “一律アップ”ではなく“評価・貢献度に応じた昇給”を設計する
- 「賃上げは小さく始めてOK」“1人だけ”や“時給10円UP”からでも動く
ここからそれぞれの取り組みについてを詳細に説明していきます。
「賃上げ原資」は“経費の見直し”と“助成金活用”でつくる
中小企業にとって最大の悩みは「賃上げの原資をどうやって捻出するか?」という点かと思います。しかし、売上を増やすのは簡単ではありません。そこでまず着手したいのが「経費の見直し」と「助成金の活用」です。
経費の見直しとは、普段当たり前に払っている支出を棚卸しし、本当に必要な支出だけに絞ることです。たとえば、使っていないサブスクリプションの整理、事務所の光熱費や通信費のプラン見直し、外注先や仕入れ先の再交渉など、実際に見直してみたら数万円単位でムダが見つかったという例は少なくありません。経費削減の意識をチーム全体で持つことで、想像以上のコストカットが実現でき、その分を賃上げ原資に充てることが可能です。
もうひとつ、必ず検討したいのが「助成金の活用」です。国や自治体では、キャリアアップ助成金や業務改善助成金など、賃上げを後押しするさまざまな制度を用意しています。特に「正社員化」「短時間労働者の処遇改善」「最低賃金引き上げ」などに取り組む中小企業向けの助成金は要チェックです。申請書類の作成はやや手間ですが、社労士や商工会のサポートを受ければ、意外とスムーズに進みます。
つまり、賃上げは自社の努力だけでなく、公的支援を組み合わせて初めて実現できる時代です。今すぐ経費の棚卸しと助成金リサーチに着手してみてください。
“一律アップ”ではなく“評価・貢献度に応じた昇給”を設計する
多くの中小企業で「賃上げ=全員一律で昇給」というイメージが根強いですが、現実には一律アップはかえってリスクになる場合もあります。一律に昇給させると、会社の体力が追いつかず経営を圧迫するほか、「頑張った人もそうでない人も同じ昇給」という不公平感が生まれやすいのです。
そこで今、多くの企業が実践し成果を上げているのが評価・貢献度に応じたメリハリ型昇給です。これは「目標達成」「新しい業務へのチャレンジ」「会社への貢献度」など、あらかじめ評価基準を定め、成果や姿勢が見える形で賃上げを行うものです。たとえば、売上貢献だけでなく日常業務の改善提案やリーダーシップ発揮も評価項目に入れると、社員一人ひとりのやる気スイッチを押すことができます。
この方法のメリットは、限られた原資でも頑張った人にしっかり還元することでモチベーションや定着率を高められることです。また評価基準を明文化し、社内に説明することで、不満や不信感を生みにくいのも大きなポイントです。
どう評価したらいいか分からないと悩む場合は、他社の事例を参考にしつつ、最初はシンプルな基準から始めて、徐々に自社流にアレンジしていけばOKです。
「賃上げは小さく始めてOK」“1人だけ”や“時給10円UP”からでも動く
「賃上げ」と聞くと「全社員一斉に月給を大幅アップしないと意味がない」というイメージがあるかもしれませんが、先ほども述べた通り賃上げの最初の一歩はとても小さくて大丈夫です。
たとえば、最初は「1人のキーマン社員だけ」「アルバイトの時給を10円だけ」など、ピンポイントで少額から始めてみる。これだけでも、「会社は社員の努力や成果をしっかり見ている」「賃上げを諦めていない」という前向きなメッセージになり、現場の士気や信頼感が大きく変わることがあります。
また、いきなり全員一律・大幅アップを目指して失敗するより、まず1人・まず10円の積み重ねの方が長続きしやすく、経営リスクも最小限で済みます。小さく始めて、少しずつ拡大していけば、会社全体のムードや成長にもつながります。
「こんな小さな賃上げで意味があるの?」と不安になる必要はありません。現実に、中小企業の成功事例の多くがピンポイントの賃上げからスタートしています。大切なのは、まず一歩踏み出すこと。あなたの会社でも、今日からできる賃上げを実践してみてください。
賃上げが難しいと感じる“本当の理由”はココにある

「うちの規模では無理」「やりたいけどできない」多くの中小企業が賃上げをやりたくてもできないと感じています。その背景には、単なる“お金がない”だけではない、複雑な現実があります。
■ 1. 利益率が低く、原資が確保できない
中小企業は大企業と比べ、売上の変動が激しく利益率も低い傾向にあります。
2025年中小企業白書によると、
「賃上げの障害として最も多かったのは“原資の確保が難しい”」
とされており、実に6割以上の企業がこの点を理由に挙げています。
(出典:創業手帳 中小企業白書2025)
売上や受注が不安定な中で、毎月の固定費である人件費を増やす決断は、経営者にとって極めて大きなリスクです。
■ 2. 取引先や市場の単価が上がらない
コスト高・物価高が続く一方で、「自社の値上げ」は簡単ではありません。
「原材料費も人件費も上がっているのに、取引先への価格転嫁が難しい」
「大手に比べて交渉力がなく、単価据え置きのまま人件費だけ増えていく」
こうした悩みは、JFC(日本政策金融公庫)の調査でも全体の7割が「価格転嫁の困難」を課題と回答しています。
(出典:JFC調査2024)
■ 3. 賃上げの“効果”が見えにくい
「賃上げしたら本当に人が定着するのか」「業績が良くなる保証はない」こうした賃上げ=即メリットのイメージが持てず、踏み出せない企業も多いです。
また、賃上げを実施しても「一時的にしか効果が続かなかった」「昇給後も結局離職者が出た」という声もあるのが事実です。労働市場が流動化し「給料以外の魅力」も求められる今、
「賃上げだけでは人が集まらない・定着しない」
という現場の不安も根強くあります(参考:求人ボックスジャーナル)。
■ 4. 社内の評価制度や昇給ルールが整備されていない
「どう昇給基準を作ればいいのか分からない」「公平性を保つのが難しい」この仕組み作りの難しさも、賃上げに踏み出せない大きな壁です。
一律昇給ではモチベーションが上がらず、成果型にすると評価の不満やトラブルになりやすい。この評価制度の設計と運用のノウハウ不足が、賃上げできない理由になっているのが実情です。
できる会社が実践している「賃上げの現実的な方法」3選

1. 経費削減・業務効率化で原資をつくる
一番取り組みやすいのが、経費の見直しや業務効率化によるコストダウンです。
例えば、ペーパーレス化やクラウド会計導入、不要な外注やサブスクリプションの整理、電気代や通信費のプラン見直しなど、固定費を減らした分だけ賃上げ原資に回す発想がポイントです。
実例:
ある食品加工会社(従業員15名)では、会計・勤怠管理をクラウド化し、年間60万円以上の事務コスト削減に成功。浮いた分をパート・社員の時給UPに還元し、定着率も大幅に改善しました。
2. 「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」など支援制度の活用
国や自治体の賃上げ支援助成金を活用するのも、無理なく賃上げを実現する現実的な方法です。「業務改善助成金」は、最低賃金+30円以上の引き上げで設備投資や原資を国が補助してくれます。「キャリアアップ助成金」は非正規社員の正社員転換や賃金UPで支給されます。
実例:
ある製造業(従業員20名)は、業務改善助成金で新しい機械を導入し生産性UP。月給+5,000円の賃上げを実現し、従業員からも高評価を得ました。
▶︎厚生労働省・業務改善助成金公式ページ
▶︎キャリアアップ助成金・活用事例
3. 「評価・役割別の昇給ルール」で納得感ある賃上げに
一律でなく、役割・貢献・スキルアップに応じて賃上げする仕組みづくりも、成功している中小企業の共通点です。
「新人はまず5,000円」「リーダー業務を担ったら+1万円」など、わかりやすい昇給ルールを作ることで、少額でも納得感の高い賃上げが実現できます。
実例:
地方の建設会社(従業員30名)は、職種ごとに昇給額と役割を明文化。小さな昇給でも「頑張りが反映される」実感が広がり、若手の定着と職場満足度が大きく向上しました。
▶︎ミライ経営実践レポート
「それでもムリ…」を乗り越える中小企業の工夫と成功事例
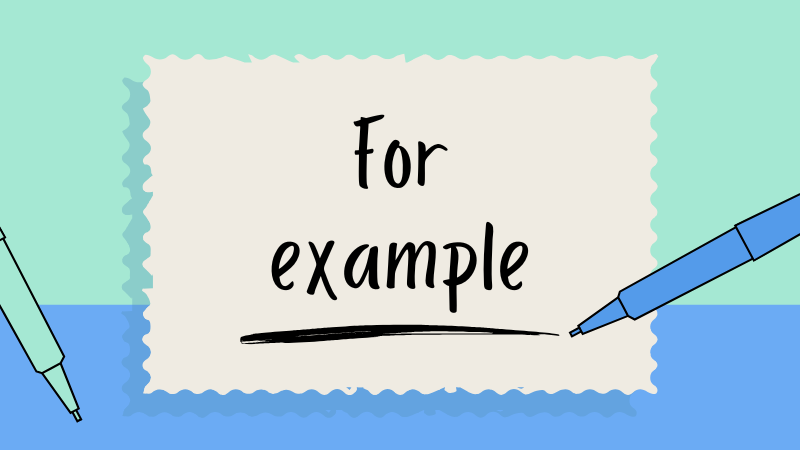
■ 1. 「社内全体で“賃上げプロジェクト化”」――全員参加型の知恵とアイデア
山形県の食品加工会社では「賃上げ=経営者だけの課題」とせず、「賃上げ原資をどう作るか」を全社員で話し合うプロジェクトとして推進しました。
「毎月の紙の伝票や工程のムダを洗い出してデジタル化」「車両・制服の管理を見直し、コストを年30万円削減」など、小さな改善案が現場からどんどん出てきました。その積み重ねで、最初は時給10円、次年度はさらに30円UPを実現しました。
■ 2. 「副業・兼業容認で原資を直接生み出す」
ある建設会社では、「会社が無理なく賃上げできるまで副業OK」とルールを見直して、社員が週末に地元農産品のネット販売やイベント出店で収入を得ることを会社ぐるみで後押ししました。
結果、「賃上げ=会社の負担」だけに頼らない、柔軟な収入アップを実現。副業・兼業の経験が本業の新規事業提案につながるなど、思わぬ副次効果もありました。
参照:中小企業白書2023・副業兼業導入事例
■ 3. 「小さなインセンティブ・福利厚生の充実で“実質”賃上げ」
岐阜県の小規模製造業では、売上や原価率の都合で大きなベースアップは困難でした。それでも「実質賃上げ」を目指し
・月3,000円分の食事補助券支給
・家族手当の新設
・有給休暇の半日取得制度
など小さなメリットを積み重ね。社員アンケートで「家計に余裕ができた」「働きやすくなった」と高評価を獲得し、離職率も半減しました。
■ 4. 「“今は無理”でも、未来の賃上げ計画を公開」
どうしても原資が足りず、今すぐ賃上げできない…という会社でも、「売上が〇〇円を超えたら」「来年この目標を達成したら」と賃上げの条件・計画を全社員に公開することは効果的です。
社長・社員で一緒にゴールを目指すことで、「いつかやる」から「みんなで達成しよう」へ変化させる。社員のモチベーションが維持でき、結果的に目標達成と同時に全員昇給を実現した会社もあります。
まとめ
賃上げは「うちには無理」と諦めるものではなく、工夫と小さな一歩から必ず実現できます。
限られた原資や支援制度を活用し、評価や福利厚生にも目を向ければ、人が辞めない・選ばれる会社へ近づくことは十分可能です。
できることから始めることが、あなたの会社の未来を変える最初の一歩です。ぜひ今日から、小さなアクションを起こしてみてください。
またこの他の記事では、労働生産性を上げるための業務効率化や、定着率アップのための福利厚生に関する記事も作成しています。併せて参考にしてください。
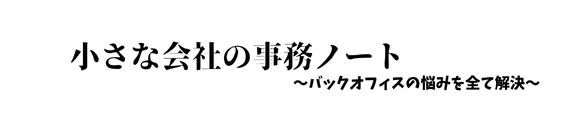
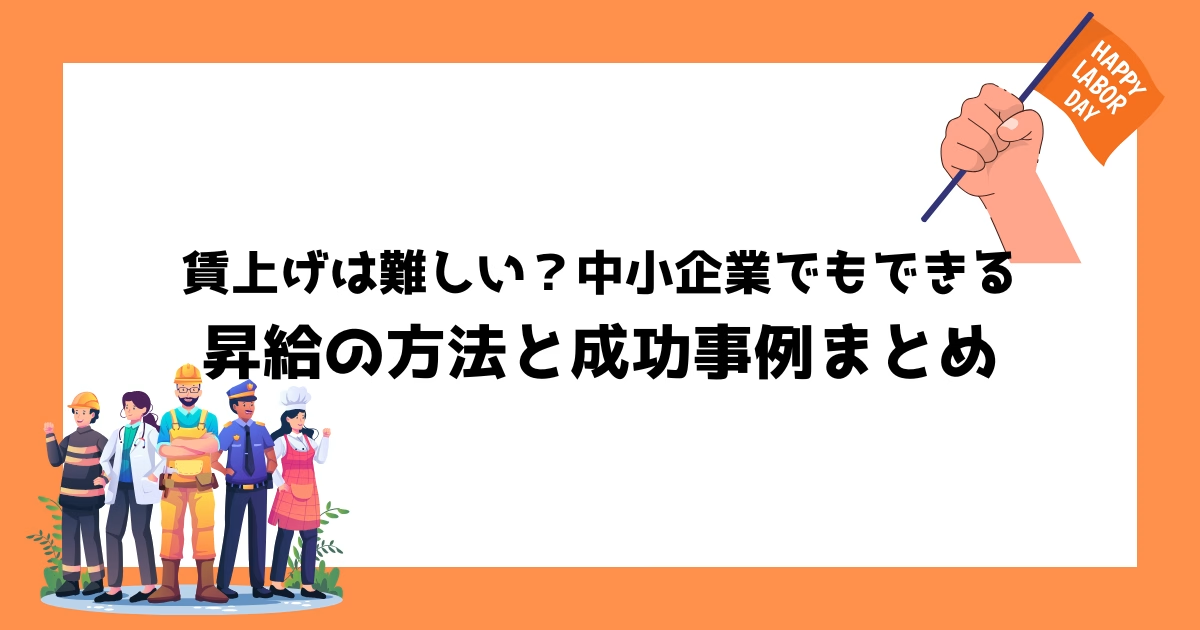
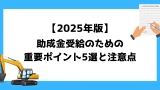


コメント