設備投資に有効な補助金活用ですが、その補助金も返還のリスクがあることはご存知ですか?
結論からお伝えすると、申請書に書かれた、「売上目標」「賃上げ目標」が未達成だった場合や、「虚偽記載」があった場合、補助金を返還する必要があります。
もうすでに設備投資をしてしまったタイミングでの返還指示は資金繰り面に大きな打撃ですよね?
また、近年では中小企業を支援する補助金が大量に新設されると同時に、補助金申請をサポートするコンサルも大量に増えています。
そういったコンサルはピンキリのため、しっかりとした採択後のフォローを受けられるコンサルもいる一方、申請書を作成して終了のコンサルも多く、そういった場合補助金の返還を迫られている場合が多いです。
私も営業に回りながら感じていたのは、補助金の返還リスクを把握しないまま補助金を活用した企業ほど、後々の返還トラブルに巻き込まれているという現実です。
今回は、そういったトラブルを回避していただくために、返金を求められるケースや、実際にあった事例、返還を回避するために重要なポイントをお伝えします。
この記事を最後まで読み、補助金をトラブルなく有効活用してください。
返還を求められるケースとは

売上目標未達成
補助金の申請書を作成する際に、その補助事業(設備投資)によって得られる売上の計画を立てます。
その際には、自社のリソースや地域の商圏、取引先との関係から定量的な判断を持って数値目標を立てているかと思います。
しかし中には、採択されることのみを目標として実現不可能な金額の売り上げ目標をたてしまった企業や、コンサルから問題ありませんよと、申請書の数字を提示されてしまった企業もいるかもしれません。
その場合国としては、その目標を達成した際の経済効果や、税収、賃上げを考慮して採択結果を発表しています。
当然未達成の場合は、当初といっていることが違うわけですから返還を迫られる可能性が非常に高いです。
賃上げ目標未達成
補助金制度の大きなテーマの一つが賃上げです。これは単なる事業計画の数字合わせではなく、賃上げという社会的な目標を経済政策(補助金政策)の中に組み込む、最近の補助金の重要な狙いの一つです。
たとえば「ものづくり補助金」や「新事業進出補助金」では、事業で得た利益がきちんと従業員に還元されているか、地域経済の活性化につながっているかを確認するため、賃金アップの達成が義務づけられています。
このため、「売上が伸び悩んだが、賃上げだけは守れた」という状況なら返還リスクは低いのに対し、「利益は出ているが、約束した賃上げを達成していない」場合には返還のリスクが非常に高いです。
補助金は企業の成長支援だけでなく、「国の賃上げ政策を現場で実現する契約」という側面が強く、計画と実績のズレには極めて厳格なチェックが行われます。
申請時は「実現可能な賃上げ幅」を冷静に見積もることが、返還リスクを防ぐ最大のポイントです。
設備の売却や廃棄
補助金で購入した設備は、形式上は企業が所有者であっても、「一定期間は国(補助金交付者)の所有物」という扱いが基本です。
これは補助金が税金でまかなわれているため、事業目的の達成や地域経済への貢献をしっかり果たしているかを、国がチェックする権利と責任を持つからです。
そのため、補助金で導入した設備を事業期間内に勝手に売却したり、廃棄したりすると、「国の財産を無断で処分した」と見なされ、補助金の全額返還やペナルティの対象となります。
たとえ設備が使わなくなった場合でも、必ず事前に事務局や担当省庁に相談し、許可や正式な手続きを経る必要があります。
このルールを知らずに設備を処分してしまい、結果的に補助金の返還を命じられたケースも少なくありません。補助金で購入した設備は「国の所有物」である、という意識を常に持ち、適切に管理しましょう。
申請書の虚偽記載
補助金の申請書に虚偽の内容を記載した場合、その影響は非常に深刻です。
虚偽申請は、実際には存在しない取引や架空の経費、過大な売上見込みの記載、取引先や実績の捏造などが該当します。
このような不正行為が発覚すると、補助金の全額返還だけでなく、加算金や延滞金が課され、企業名や代表者名の公表、今後数年間の補助金申請資格の停止、さらには刑事告発まで至るケースもあります。
国の補助金は、税金という公共資産から支出されているため、信頼に基づく契約が前提です。虚偽申請はその信頼を根本から損ねる行為であり、極めて厳格に取り締まられます。
申請段階では「多少盛っても大丈夫だろう」と安易に考えるのではなく、事実に基づいた内容を正確に記載することが、補助金を安全に活用する第一歩です。
実際の返還事例
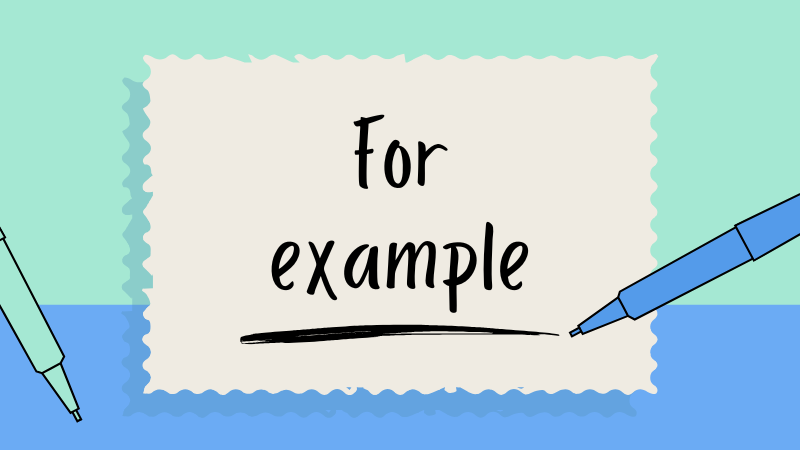
1. 賃上げ目標未達成による返還命令の詳細事例
【業種・企業規模】
- 業種:精密機械部品製造業(従業員20名、地方中小企業)
【設備投資額・申請内容】
- 補助金申請額:2,000万円
- 投資内容:新型NC旋盤2台の導入による自動化ラインの構築
- 申請時の目標:
・3年後までに従業員の平均給与を年率1.5%以上アップ
・新分野受注により売上高30%増加
・地元新卒者の採用枠拡大
【実際の経過】
- 補助金採択後、設備は納入・稼働。
- しかしコロナ禍の受注減・原材料高騰の影響で売上・利益が伸び悩み、目標として掲げていた賃上げを実現できず。
- 補助金交付から2年後の「フォローアップ報告」で未達成が判明。
- 事務局より「計画賃上げ未達のため交付規程に基づき補助金全額(2,000万円)の返還を命じる」と通知を受領。
- 返還命令の理由通知には「賃上げ目標未達(年率1.5%未満)」「給与台帳・証憑で裏付け可能」と明記
2. 虚偽申請書作成による返還命令の詳細事例
【業種・企業規模】
- 業種:機械金属加工業(大阪府、従業員10名)
【設備投資額・申請内容】
- 補助金申請額:2,400万円
- 投資内容:最新鋭CNCフライス盤の導入(と虚偽記載)
- 申請内容の虚偽:
・実際には未発注・未納入の設備について「○月○日取得済み」と記載
・事業実績報告も架空伝票・偽造請求書を添付
【実際の経過】
- 書面審査・現地調査で「納品実績・設置現場・会計帳簿に不一致」が発覚。
- 事務局によるヒアリング調査で「取引先への裏付け照会」「設備写真・設置状況調査」も実施され、不正の全貌が判明。
- 補助金2,400万円全額返還+加算金命令、企業名と代表者名を公式公表。
- 今後5年間の補助金・助成金申請資格停止。
補助金の返還を回避するためには

実現可能な事業計画立案
補助金の返還リスクを最小限に抑えるためには、何よりも「実現可能な事業計画」を立てることが不可欠です。
申請時は、採択を目指すあまり大きな売上や利益、賃上げ目標など「理想」を並べてしまいがちですが、補助金は採択されてからが本番です。計画通りに進まなかった場合、目標未達を理由に返還命令が出ます。
まず自社の人員・設備・商圏・取引先・市場動向など現実的なリソースを洗い出し、過去実績や今後の課題も客観的に分析しましょう。そのうえで、「最も確実に達成できるライン」を数値化し、無理のない目標を設定することが重要です。
もし申請書の段階で不安な数字があれば、専門家や商工会・事務局に事前相談するのも有効です。
採択ありきの計画ではなく、「本当に達成できる内容」を積み重ねることで、結果的に補助金の返還リスクを大幅に減らすことができます。
事務局や認定支援機関への相談
補助金を安全に活用し返還リスクを回避するためには、事務局や認定支援機関への定期的な相談が非常に重要です。
申請書の作成段階だけでなく、採択後の事業実施期間中や、実績報告のタイミングでも、疑問点や判断に迷う部分があれば早めに問い合わせましょう。補助金の制度やルールは年度ごとに細かく変更されることも多く、自己判断で進めてしまうと思わぬミスにつながることもあります。
また、現場でよくある疑問点は、「この経費は対象になるのか」「設備の処分や移動は大丈夫か」などの細かなケースです。こうした場面でも、事務局や認定支援機関に事前に確認を取ることで、後になって返還を命じられるリスクを大幅に減らせます。
分からないことは「すぐ聞く」が鉄則です。相談の記録や指示内容は必ず保存しておき、何かあった場合の証拠にも活用しましょう。
報告体制の構築
補助金を受けた後の返還リスクを最小限に抑えるには、社内外の「報告体制の構築」が欠かせません。
補助金は申請・採択時点で終わりではなく、事業実施期間中や補助事業終了後も実績報告や目標達成状況の報告が義務づけられています。
例えば、設備投資後の運用記録、賃上げや売上目標の進捗チェック、帳簿や証憑の整理・保存など、日常的に証拠を残す意識が必要です。
また、担当者が異動・退職した場合にも情報や管理方法がきちんと引き継がれるように、マニュアルやチェックリストを整備して、必要に応じて外部の専門家とも連携しましょう。
フォロー体制が確立されていれば、不測のトラブルや事務局からの調査要請にも迅速に対応でき、結果的に返還リスクの回避につながります。日々の運用・管理を見える化し、チーム全体で補助金を守る姿勢が大切です。
まとめ
補助金はもらって終了ではありません。
その後にしっかりと事務局と連携をとりながら、事業化状況報告の実施期間を終了し、設備を自社で取得して初めて終了になります。
返還トラブルなく補助金を活用し、積極的な設備投資で売上利益を拡大していきましょう。
この他の記事では、補助金で車を買う方法や、今おすすめの補助金を案内しています。併せて読んでみてください。
補助金で車は買える?2025年最新5つの例外パターン
2025年中小企業向けおすすめ補助金3選と今から準備すべきこと【保存版】
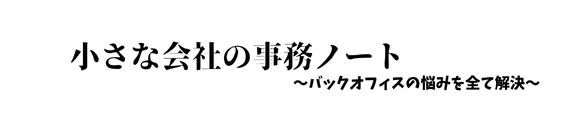

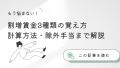
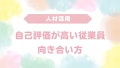
コメント