人を採用しただけで国からお金がもらえると嬉しくないですか?
これまで数多くの中小企業の経営者から頂いた相談の中で、「採用した時に使える助成金があるって聞いたけど、うちってこれ使えるの?」という声を何度も伺ってきました。
人材不足が深刻化する一方で、求人広告や人件費の負担が重く、「できるだけコストを抑えて採用したい」と考えている方がほとんどです。
実は、国や自治体では採用しただけで受け取れる助成金制度がいくつも用意されています。うまく活用できれば、採用コストの負担を大幅に減らしつつ、理想の人材確保も実現できます。
この記事では、中小企業が今すぐ使える採用助成金の種類や活用方法、申請時のポイントまで具体的に解説します。実際に助成金を活用して採用コスト削減に成功した会社の事例も紹介していますので、ぜひ最後まで参考にしてください。
採用時に使える助成金とは?最新トレンドと活用メリット

「助成金=設備投資や雇用維持だけ」というイメージを持っている方も多いですが、実は“新しく人を採用した”タイミングこそ、もらえる助成金が豊富です。国や自治体は中小企業の人材確保を強く後押ししており、「正社員化」「若手・シニア・ひとり親などの雇用」「研修・教育付き採用」など、多様な制度が毎年拡充されています。
こうした助成金を活用すれば、求人広告や研修費、初期の人件費など“採用にかかる大きなコスト”を国が一部補助してくれるため、経営の負担をグッと軽減することが可能です。たとえば、非正規から正社員に転換すれば1人あたり最大57万円、一定条件の新規雇用で数十万円が支給されることも。
採用時の助成金は「申請のタイミング」と「活用方法」を押さえれば、想像以上に利用しやすいのが特徴。今や、多くの中小企業が人材確保の“必須アイテム”として活用しています。知らずにスルーするのは本当にもったいないので、ぜひ一度チェックしてみてください。
中小企業が必ずチェックすべき主な採用助成金5選
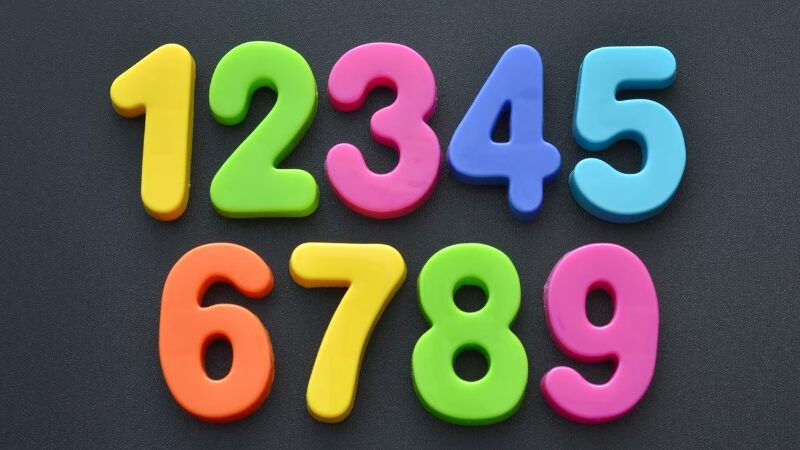
1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- もらえる金額
1人あたり最大57万円(中小企業の場合/2024年度) - 条件
有期雇用・パート・アルバイト等の非正規社員を正社員へ転換し、6か月以上継続雇用 - 対象
正社員転換する従業員(転換前に6か月以上雇用されていることが原則) - 注意点
転換前に「キャリアアップ計画」の提出が必要。転換日や手続きのタイミングに注意。就業規則・労働契約書の整備も必須
2. トライアル雇用助成金
- もらえる金額
月額4万円×最大3か月(1人あたり計12万円) - 条件
ハローワーク等で紹介された「就職困難者」を原則3か月間試用雇用し、その後も継続雇用を目指す - 対象
若年層(25~44歳)、シングルマザー、障害者、長期離職者等 - 注意点
ハローワーク経由の求人が必須。採用前からトライアル雇用の意図を明示しておく必要あり
3. 特定求職者雇用開発助成金
- もらえる金額
1人あたり最大60万円(中小企業の場合、短時間労働者は最大40万円) - 条件
ハローワーク紹介による高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母等を新規雇用し、1年以上継続雇用 - 対象
上記「就職困難者」カテゴリーに該当する新規採用者 - 注意点
雇用契約書・賃金台帳など証拠書類の整備が必須。短期間の離職があると受給不可
4. 地域雇用開発助成金
- もらえる金額
雇用人数や地域、内容により異なる(例:1事業所最大600万円/3年など) - 条件
厚労省が指定する地域(過疎地など)に新たに事業所を設置し、一定数以上の雇用を創出 - 対象
対象地域内で新規雇用される労働者 - 注意点
地域・雇用人数・雇用維持要件など細かい基準あり。事前計画・書類作成が必要で、審査が厳しめ
5. 人材開発支援助成金(特定訓練コース等)
- もらえる金額
研修経費の一部(例:経費助成45%+賃金助成1時間あたり760円/中小企業の場合 ※詳細はコースによる) - 条件
雇入れ後6か月以内の従業員に、OFF-JT(外部研修等)を一定時間以上実施 - 対象
新規採用者を含む正社員・契約社員(対象コースにより異なる) - 注意点
事前計画・申請が必須。研修実施証明や受講記録、賃金台帳等を整備しないと受給不可
助成金活用のポイントと注意点

助成金は、知っている会社だけが得をして、知らない会社は“もらい損ねてしまう”制度です。しかし、「申請さえすれば簡単にもらえる」と思っていると、思わぬ落とし穴にはまることも少なくありません。ここでは、助成金を上手に活用するためのポイントと、注意したい“よくあるミス”を紹介します。
1. 申請前に“必ず”要件やガイドラインを細かく確認する
助成金の申請において最も大事なのが、「自社が本当に助成金の要件を満たしているか」を事前にしっかり確認することです。助成金ごとに申請できる企業や雇用形態、従業員数、賃金水準、雇用期間など細かな条件が厳密に定められており、少しでも条件から外れていると申請そのものが受理されません。
また、最新のガイドラインや募集要項は毎年内容が改定されるため、過去の経験や他社の事例をそのまま参考にするのは危険です。制度によっては「申請前に事業を開始すると対象外」「一定の雇用期間経過後に申請可能」など、タイミングや順序が非常に重要なケースもあります。
公式サイトや厚生労働省のガイドライン、Q&A、FAQも必ずチェックし、疑問点は事前に管轄の労働局や社労士に確認しましょう。
助成金は「まず要件を細かくチェックする」ことが、受給への第一歩です。
2. 書類の不備・記入漏れが最も多い落とし穴
助成金申請で最も多くの企業がつまずくのが、「書類の不備」や「記入漏れ」です。助成金の審査は非常に厳密で、提出書類が一つでも不足していたり、記載内容に不明瞭な点や誤りがある場合は、即座に「不支給」や「差戻し」となってしまいます。
たとえば、「雇用契約書」「賃金台帳」「出勤簿」「タイムカード」「就業規則」「給与支払明細」など、求められる書類は多岐にわたります。それぞれ最新のもの、対象期間を満たすものが必要であり、記載内容がガイドラインに沿っているかどうかも厳しくチェックされます。
さらに、電子申請の場合は「PDF化したファイルの不備」「データが壊れている・読めない」など、デジタルならではのトラブルも増えています。
このような書類のミスは、申請者本人が気づかないまま進んでしまうことも多いので、提出前には必ず複数人でチェックリストを使って確認することが大切です。
3. 「実態が要件を満たしていない」と発覚しやすい
助成金は、申請時の書類が一見揃っていても、「実態が要件を満たしていない」と後から発覚するケースが少なくありません。
たとえば、「契約書は作成したが、実際の働き方が契約内容と違う」「賃金台帳の金額と実際の支払いが一致していない」「正社員化の要件を満たすと申請したが、実態はパート契約のままだった」など、“形式”と“実態”のズレは行政による審査で特にチェックされます。
最近は、助成金の審査や監査が厳格化されており、申請書類だけでなく、実際の勤務記録や給与明細、業務実態のヒアリング、現地調査まで行われるケースも増えています。
また、申請時点で「過去に同じ助成金を受けていない」「一定期間以上継続雇用している」といった細かい要件を見落としていると、後から審査で不支給が決まることも多いです。
「とりあえず申請してみて、後で調整すればいい」といった曖昧な姿勢は非常に危険であり、不正と判断されれば今後の助成金申請自体ができなくなるリスクもあります。
助成金の活用では、「書類を整えるだけ」ではなく、実際の雇用や労務管理、給与支払い、就業規則の運用まで実態が要件どおりか、必ず自社で確認することが不可欠です。
4. 申請のタイミング・期限にも注意
助成金の申請では「いつ申請するか」「どのタイミングで書類を出すか」が受給できるかどうかを左右する最大のポイントです。多くの助成金は、“採用前”や“雇用契約締結前”に事前計画書や申請書を提出することが必須になっています。たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、転換前にキャリアアップ計画の提出が必要ですし、トライアル雇用助成金でも「雇用前にトライアル雇用求人としてハローワークに申し込む」ことが絶対条件です。
申請のタイミングを一日でも間違えると「すでに雇用してしまっているので対象外」「計画書の提出が遅れて無効」といったケースになり、せっかくのチャンスを逃してしまいます。これは、過去の実績や事後報告では認められず、“事前準備”が不可欠であるという助成金ならではの厳しさです。
また、多くの助成金は受付期間や募集枠が設定されており、「年度内で締め切り」「予算が上限に達し次第終了」といったパターンも多いです。早めに申請しないと、年度途中で受付終了となることも珍しくありません。
このように、助成金の申請では“計画・雇用・実績・報告”など各段階で細かい期限が設けられているため、スケジュール管理を徹底し、早め早めに準備を進めることが成功のカギです。
5. 受給後も報告・書類保存が必要
助成金は「申請して受け取ったら終わり」ではありません。多くの助成金制度では、受給後も定期的な報告や関連書類の一定期間保存が義務付けられています。
また、給与台帳や雇用契約書、出勤簿、支払明細、研修記録、社内の通知文書など、助成金申請時や受給後の“証拠書類”も数年間(多くは5年間)保管が必要です。 これは、後日行政から「実地調査」「書類提出」を求められた際、すぐに提出できるようにするためです。
たとえば、数年後に抜き打ち調査が入り、「保存書類が見つからない」「支給内容と実態にズレがあった」となった場合は、受給した助成金の全額返還だけでなく、悪質と判断されればペナルティや社名公表の対象になることもあります。
さらに、会社の担当者が異動・退職した場合でも確実に書類を引き継げるよう、社内で一元管理のルールを作ることが重要です。
助成金の適正な活用には、「受給後の管理」まで含めた準備と意識が不可欠です。これを怠ると、せっかく得たメリットを台無しにしてしまうことにもなりかねません。
申請から受給までの流れと実務のコツ

助成金の申請は、「知っているだけ」ではもらえません。実際の申請手続きには細かな段取りやルールがあり、ここでつまずいて受給できないケースも珍しくありません。そこで、中小企業が助成金を“確実にもらう”ための流れと、実務で押さえるべきポイントを解説します。
1. 申請前の下準備(計画・情報収集)
まずは「自社でどの助成金が使えるか」「どの雇用や採用形態が対象か」を調べ、公式ガイドラインや募集要項を熟読しましょう。この段階で社労士など専門家に初回相談するのもおすすめです。
2. 必要書類の準備と整備
多くの助成金で「雇用契約書」「出勤簿」「賃金台帳」などの証拠書類が求められます。日々の労務管理を正確に行い、書類の抜け・誤記がないか早めにチェックすることが大切です。
3. 計画書・申請書類の提出
助成金によっては「雇用前」「雇用後」など提出タイミングが異なります。計画書・申請書類は正確かつ期限厳守で提出しましょう。不明点があれば社労士や商工会議所などに事前相談するのが安心です。
4. 行政の審査・現地確認対応
申請後は行政の審査が行われ、必要に応じて追加書類の提出や現地調査が行われます。申請内容と実態が一致しているか、証拠書類に不備がないかなど、万全の準備をしておきましょう。
5. 受給・アフターフォロー
無事に受給できた後も、事業の進捗報告や証拠書類の保存など、継続的な管理が求められます。助成金によっては数年間の保存義務があるため、管理ルールを徹底してください。
まとめ
採用活動における助成金の活用は、限られた予算で人材を確保したい中小企業にとって大きな武器になります。今回ご紹介したポイントや制度をしっかり押さえ、計画的に活用することで、採用コストを抑えつつ、より自社に合った理想の人材を採用することが可能です。
制度の最新情報を常にチェックし、ミスなく手続きを進めることで、会社の成長を後押しする採用戦略を実現しましょう。
また、この他の記事では助成金受給のための重要ポイントや、人気の補助金についてもまとめています。併せて参考にしてください。
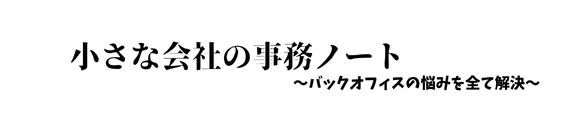
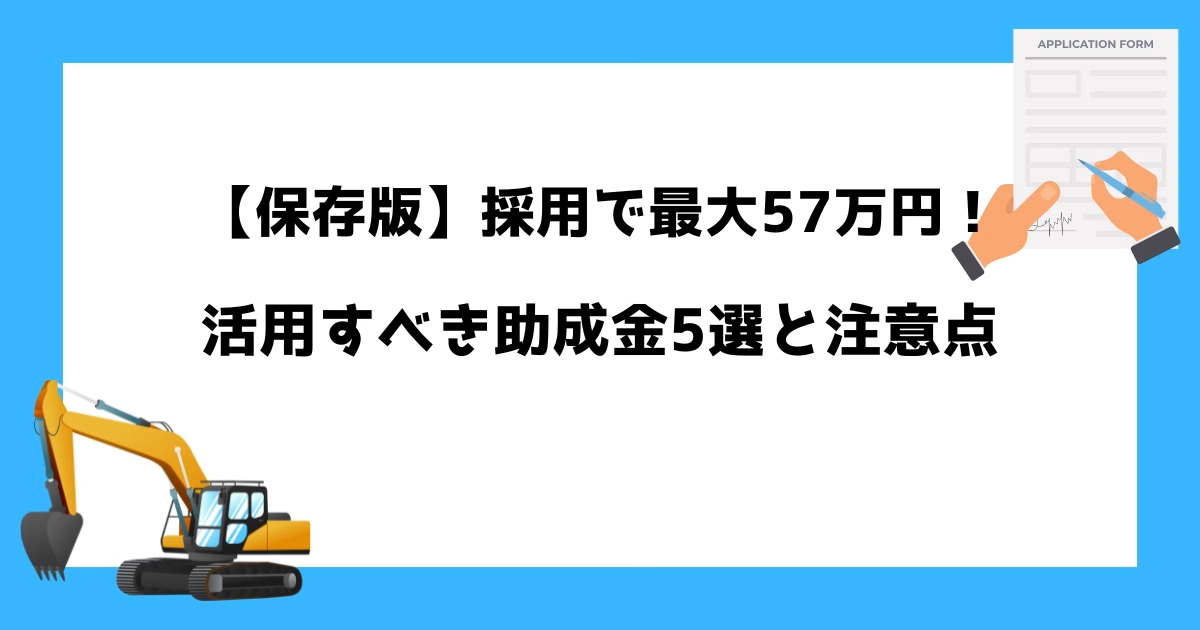

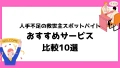
コメント