自己評価が高いというとマイナスなイメージを持つ人の方が多いのではないでしょうか。
実際私も「自己評価が高い=プライドが高い、口だけ、評価と働きが一致しない」というマイナスなイメージを持っていました。
というのも、同じチームにかなり自己評価の高い男がいたのですが、あまり仕事のできる人間ではなく、コミニュケーションをとるのも苦手でした。
プライドが高いことや、自己評価が高いことは、一概に悪いとは言えませんが、度が過ぎると周囲に悪影響を与えますよね。
しかし、この本を読んでからプライドが高い人間の心理がわかり、コミニュケーションをスムーズにとることができるようになった結果自然とチーム内の雰囲気も良くなり、成績が上がっていきました。
おすすめなので、時間のある方はぜひ読んでみてください。
この記事では、自己評価が高い従業員の扱いに悩まれている方向けに、「自己評価が高い人はどんな人間なのか」、「どう向き合えばいいのか」「活躍させるにはどうしたらいいのか」を心理学の観点から解説します。
自己評価が高い人とは

自信過剰になりやすく、現実を見誤ることがある
自己評価が高すぎる人は、自分の能力や成果を過大評価してしまいがちです。心理学では「自己奉仕バイアス(self-serving bias)」と呼ばれ、自分に都合のよい情報ばかりを受け入れ、失敗の原因を他人や環境のせいにする傾向があります。この結果、課題やリスクを過小評価して現実的な対処ができず、仕事や対人関係で失敗を繰り返すことがあります。中小企業では経営資源が限られているため、リーダーや担当者が自信過剰になると無謀なプロジェクトや強引な意思決定につながりやすく、組織全体の損失やトラブルを引き起こす危険も高まります。
現状維持バイアスに陥りやすい
自己評価が高い人は「今の自分で十分にできている」という安心感から、現状のやり方や成功体験に固執しやすい傾向があります。心理学では「現状維持バイアス(status quo bias)」として知られ、新しい挑戦や変化を避けてしまう原因となることがあります。自分の方法がベストだと思い込むことで、外部環境の変化に対応できず、時代遅れや業績悪化を招くリスクもあります。中小企業の経営や現場運営では、日々の変化や競争が激しいため、柔軟な変革意識が不可欠です。自己評価の高さが「成長の停滞」につながらないよう注意が必要です。
失敗時のダメージが大きく、自己防衛に走る
自己評価が高い人ほど、失敗や批判に直面したとき「自分のプライド」を守るために強い自己防衛反応を示すことがあります。心理学では「防衛的悲観主義(defensive pessimism)」や「認知的不協和」が働きやすいとされ、現実逃避や責任転嫁、言い訳などの行動が目立ちやすくなります。こうした態度がチーム全体の士気や信頼を損なう要因にもなり得ます。特にリーダーが自己弁護や責任回避に走ると、現場の本音や改善提案が通りにくくなり、組織の停滞や離職の増加にもつながりかねません。素直な失敗認知と反省力が重要です。
周囲との摩擦や孤立を生みやすい
自己評価が高い人は、自分の意見ややり方に強いこだわりを持つため、時に「上から目線」や「自己中心的」と受け取られることがあります。心理学の「ナルシシズム(自己愛傾向)」とも関連し、他人を見下す態度や共感の欠如、マウンティング行動が見られる場合もあります。中小企業のような少数精鋭型の組織では人間関係の密度が高く、こうした言動が対立や派閥、孤立の引き金になることが少なくありません。結果的に優秀な人材ほど周囲との信頼を築けず、組織に居場所をなくしてしまうリスクがあります。
他者の意見や助言を軽視しやすい
自己評価が高い人は「自分は正しい」「自分ならできる」という思いが強く、他者からのアドバイスや異なる意見を受け入れにくい傾向があります。心理学の「認知的不協和理論」によれば、人は自分の信念と矛盾する情報を無意識に排除しがちです。結果として、客観的なフィードバックや必要なサポートを逃してしまい、独断専行になりやすいのがデメリットです。特に少人数体制での連携や情報共有が重要になる組織では、一人の自信過剰が意思決定ミスや職場の空気の悪化につながる場合があります。時には周囲の声に耳を傾ける柔軟さも必要です。
自己評価が高い人との向き合い方
自己評価が高い人と向き合う際は、まず相手の自信や実績をしっかり認め、リスペクトの気持ちを持って接することが大切です。
頭ごなしに否定せず「その考え方も一理あるね」と受け止める姿勢を見せることで、相手もこちらの意見に耳を傾けやすくなります。意見が異なる場合も、「どうしてそう考えたのか教えてくれる?」と建設的な質問で対話を深めましょう。
フィードバックを伝える際は、抽象的な批判ではなく事実や成果に基づき、具体的な改善点を添えて伝えることが効果的です。
また、自己評価が高い人の行動力やチャレンジ精神を活かし、協働の場に巻き込むと、組織やプロジェクトにもプラスの影響が生まれます。場合によっては適度な距離感を意識し、お互いが心地よく働ける関係を築くことも大切です。否定せず、認め合いながら、対話と成長につなげる関係を目指しましょう。
自己評価が高い人を活躍させるには
明確な目標や期待を伝える
自己評価が高い人は「自分はできる」という自信がモチベーションの源泉です。その力を成果につなげるには、何を期待されているか、どんなゴールを目指せばいいかをはっきり示すことが不可欠です。目標が曖昧だと自信が空回りしやすくなりますが、明確な指針があれば、持ち前の主体性と集中力を仕事の達成へ向けて効果的に活かすことができます。
強みや成果をしっかり認めてフィードバックする
心理学的に「承認欲求」は誰しも持っていますが、自己評価が高い人ほど他者からの評価が自信と直結します。良い仕事ぶりや工夫、成果をきちんと評価し伝えることでモチベーションがさらに高まり、より高い成果を目指す好循環を生み出します。逆に、評価が曖昧だと意欲低下や反発を招くことも。
暴走を防ぐために、定期的な対話と軌道修正を行う
自信が強すぎると独りよがりや周囲との摩擦、ミスの見落としにつながるリスクもあります。そこで定期的に話し合いや進捗確認の機会を設けることで、方向性がズレていないかを一緒に確認し、必要なときは冷静に軌道修正できます。これにより、本人の成長とチームの調和を両立できます。
まとめ
働き手の少ない現代では、会社にいるすべての人間に活躍してもらうことが不可欠です。
そして、人間にはそれぞれ適性があり、特不得意もあります。
すべての人材に活躍してもらうために、人の特性を知り、うまく適材適所に当てはめていきましょう。
また、この他の記事では、採用に関する情報や、満足度を高める福利厚生に関しても情報を発信しています。併せて参考にしてください。
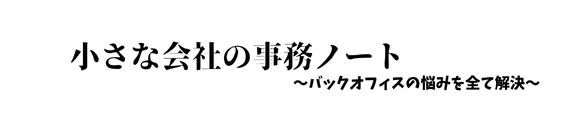
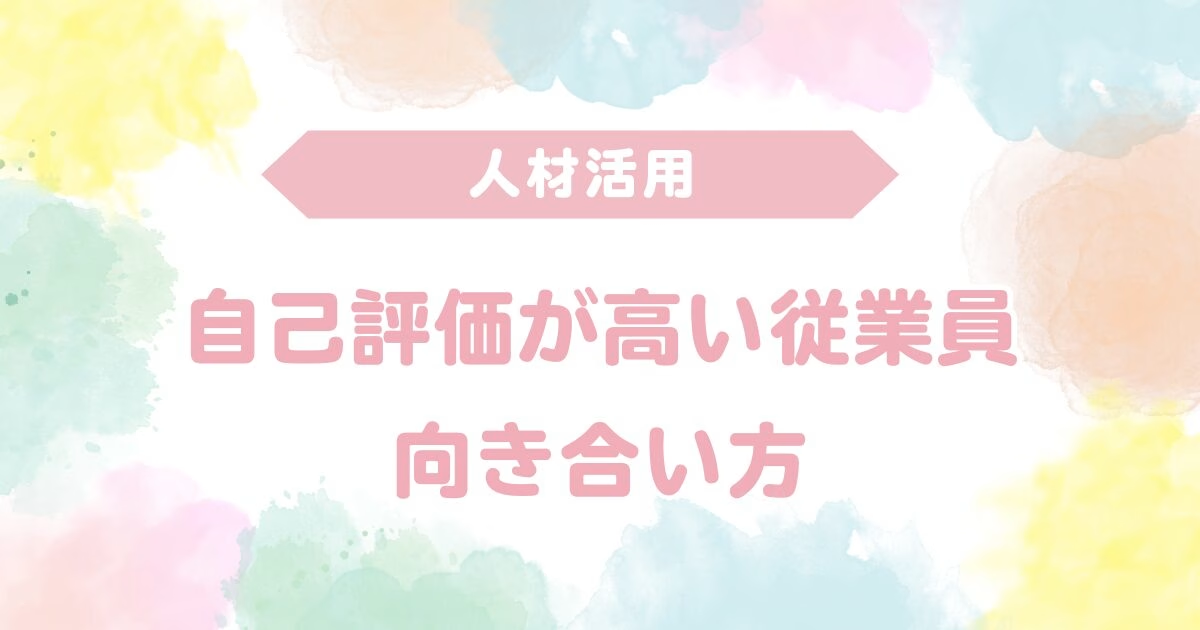
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a24312c.072751cd.4a24312d.17f9563c/?me_id=1213310&item_id=17142767&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0910%2F9784569820910_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


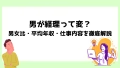
コメント