まず知っておくべき「解雇の原則」とリスク
従業員の解雇は、経営者の一存で自由に行えるわけではありません。
日本の労働法は労働者保護を基本とし、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合」でなければ解雇は無効とされます(労働契約法第16条)。
このため、解雇を進めるには、以下の3つを満たす必要があります。
- 客観的な事実に基づく理由(就業規則違反・能力不足・経営上の必要性など)
- 社会通念上の相当性(一般的な常識から見て妥当であること)
- 適正な手続きの実施(指導・警告・記録の保存)
不当解雇と判断されやすいケース
- 解雇理由が抽象的(「やる気がない」「雰囲気が合わない」など)
- 証拠や記録がない
- 妊娠・産休・育休を理由とした解雇
- 労働組合活動や内部通報を理由とした解雇
- 即日口頭での解雇通告
注意:これらのケースでは、裁判や労基署対応で企業側が不利になる可能性が高いです。
不当解雇が企業にもたらす主なリスク
- 復職命令(地位確認請求)
→ 解雇が無効とされ、従業員が復帰するケースがあります。 - 未払い賃金の支払い
→ 解雇日から判決までの給与(場合によっては数百万円〜数千万円)を支払う義務が発生。 - 慰謝料・損害賠償
→ 精神的苦痛や経済的損失に対する賠償命令の可能性。 - 労基署の是正勧告・企業名公表
→ 採用活動や取引先からの信頼失墜につながる。
裁判・労基署対応が経営に与える影響
法的トラブルは金銭的負担だけでなく、経営者やバックオフィスの時間を大きく奪います。
さらに、社内の士気低下や他従業員への不安波及、SNSやメディア報道によるレピュテーションリスクも軽視できません。
まとめポイント
- 解雇は「最終手段」であり、感情ではなく証拠と手続きが必須
- 事前に就業規則や雇用契約書を確認し、記録化を徹底する
- リスクを最小化するために、早期の専門家相談が有効
従業員を辞めさせる方法は4パターン
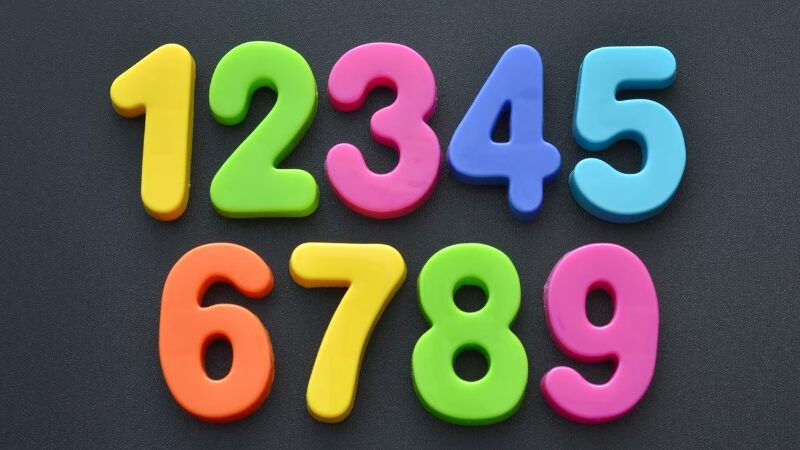
従業員を辞めさせる方法は、大きく分けて以下の4つです。
- 合意退職(双方同意)
- 普通解雇(能力不足・勤怠不良など)
- 懲戒解雇(重大な違反)
- 契約期間満了による退職(有期契約の場合)
それぞれ適用できる条件や手続きが異なり、誤った進め方は不当解雇リスクを高めます。
以下で、中小企業の経営者やバックオフィス担当者が実務で迷わないよう、特徴と注意点を解説します。
① 合意退職(双方同意)
最もトラブルが少なく、円満に進めやすいのが合意退職です。
会社と従業員が話し合い、退職日や条件に合意した上で契約を終了します。
向いているケース
- 人間関係の悪化やミスマッチがあるが、大きな規律違反はない場合
- 双方が冷静に話し合える関係が残っている場合
メリット
- 裁判や労基署トラブルになりにくい
- 解雇予告手当が不要な場合が多い
デメリット
- 従業員が同意しなければ成立しない
必要書類・手順
- 退職合意書の作成(退職日・理由・条件を明記)
- 面談記録の保存
- 複数回の面談で慎重に進める
注意:強制的に迫ると「退職強要」とされる可能性があります。
② 普通解雇(能力不足・勤怠不良など)
普通解雇は、能力不足や勤務態度不良、職務怠慢などを理由に行う解雇で、就業規則の定めに基づきます。
法的要件(労働契約法第16条)
- 客観的に合理的な理由がある
- 社会通念上相当である
- 適正な手続きを経ている(改善指導・警告・記録など)
向いているケース
- 繰り返しのミスや遅刻・欠勤が改善されない
- 能力不足が業務に支障を与えている
メリット
- 就業規則の範囲内なら進めやすい
デメリット
- 証拠や記録が不十分だと不当解雇になるリスクが高い
必要書類・手順
- 注意書・警告書の発行
- 面談記録(日時・内容・出席者)
- 解雇予告または予告手当(30日分)
③ 懲戒解雇(重大な違反)
懲戒解雇は、横領・暴力・情報漏洩・重大な規律違反など、会社に著しい損害を与える行為に適用されます。
向いているケース
- 犯罪行為や重大な背任行為があった場合
- 社会的信用を著しく損なう行為
メリット
- 即時解雇が可能(場合によって退職金不支給)
デメリット
- 訴訟リスクが非常に高い
- 社会的制裁が大きく、後の雇用にも影響
必要書類・手順
- 違反行為の証拠(映像・記録・証言など)
- 就業規則に明確な規定があることを確認
- 弁明の機会を与える(懲戒委員会の開催など)
注意:懲戒解雇は「最終手段の中の最終手段」です。
④ 契約期間満了による退職(有期契約の場合)
有期雇用契約の期間満了により、契約を更新せず退職となる方法です(雇止め)。
法的要件(労働契約法第17条)
- 契約書に期間を明記
- 更新しない場合は30日前までに予告
- 長期更新を繰り返している場合は「期間の定めなし」とみなされる可能性
向いているケース
- 業務終了やプロジェクト終了が明確な場合
- 契約更新時に業務能力や態度の問題がある場合
必要書類・手順
- 契約書・更新履歴の確認
- 雇止め通知書の発行
まとめ
- トラブルを避けるなら「合意退職」が第一選択肢
- 普通解雇・懲戒解雇は証拠と手続きがカギ
- 有期契約満了でも、通知義務や更新実績には要注意
解雇前に必ず行うべき5つの準備
従業員の解雇は、感情や印象ではなく証拠と法的手続きに基づいて進める必要があります。
これを怠ると、不当解雇として裁判で争われ、復職命令・未払い賃金の支払い・慰謝料請求といった大きな損害が発生します。
安全かつ合法的に解雇を進めるために、以下の5つの準備ステップは必須です。
1. 就業規則と雇用契約書の確認
目的:解雇事由が会社規程に沿っているか確認するため。
- 就業規則に該当する解雇事由が明記されているか
- 契約形態(正社員/有期契約/パート)と契約期間の有無
- 解雇予告や懲戒処分の規定内容
リスク回避ポイント
規程にない理由での解雇はほぼ確実に無効判定。まずは社内規程と契約内容の整合性確認から着手します。
2. 問題行動・能力不足の記録化
目的:客観的な事実に基づく解雇理由を立証するため。
- 勤怠不良:遅刻・欠勤の日付・回数・理由
- 業務ミス:発生日時・内容・損害の有無
- 顧客・同僚からの苦情や報告
リスク回避ポイント
証拠がなければ裁判では「経営者の主観」と判断されます。日付+内容+証拠物を必ず残します。
3. 改善指導・研修・配置転換
目的:解雇前に改善の機会を与えた事実を残すため(労働契約法第16条)。
- 業務改善指導(口頭+書面)
- 能力向上研修やOJTの実施
- 他部署や軽作業への配置転換
リスク回避ポイント
一度の指導だけでは「改善の機会不足」とされます。複数回・一定期間(目安3か月)の改善措置が望ましいです。
4. 警告書・通知書の発行
目的:改善が見られなかったことを公式に記録し、解雇予告の法的義務を果たすため(労働基準法第20条)。
- 警告書:具体的な問題点と改善期限を明記
- 解雇予告通知書:解雇日・理由・予告手当の有無を明記(30日前まで通知が必要)
リスク回避ポイント
書面は本人に直接交付し、署名または送達記録を残します。口頭通知だけでは証拠能力が弱いです。
5. 面談記録・証拠の保管
目的:後のトラブル時に備え、すべての経緯を立証可能にするため。
- 面談日時・場所・参加者・発言内容の記録
- メール・チャットでのやり取り保存
- 警告書や通知書のコピー保管
リスク回避ポイント
証拠の保管期限は最低でも3年間(労働基準法の時効)を目安にします。
まとめ
- 解雇は「証拠」と「手続き」が命綱
- 上記5つを行わないまま進めると、不当解雇として逆に損害賠償請求を受ける可能性大
- 書類・記録・証拠の三位一体管理が経営リスクを減らす
合法的に解雇するための条件チェックリスト
解雇は会社の一存では決して成立しません。
労働契約法第16条により、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効となります。
条件を満たさず解雇すると、不当解雇として復職命令・賃金支払い・損害賠償などの深刻な結果を招く可能性があります。
以下のチェックリストで、あなたのケースが合法的な解雇に該当するかを確認しましょう。
合法解雇チェックリスト(Yesならチェック)
- 就業規則や雇用契約書に、今回の解雇理由が明記されている
→(例)勤怠不良、職務怠慢、規律違反などが具体的に規定されている - 解雇理由を裏付ける証拠が揃っている
→ 勤怠記録、業務ミス報告書、顧客クレーム記録など - 改善の機会を複数回与えた(目安:3か月以上)
→ 指導記録、研修履歴、配置転換の実施記録 - 警告書や注意書を文書で交付し、記録を保管している
→ 署名付き、または配達記録付き郵送 - 解雇予告を30日前に行った、または予告手当を支払った(労基法第20条)
- 懲戒解雇の場合、就業規則に規定されており、弁明の機会を与えた
- 契約社員の場合、契約満了の30日前までに更新しない旨を通知した(労働契約法第17条)
- 解雇理由が差別的・報復的でない
→ 性別、年齢、組合活動、内部通報を理由としていない - 過去の処分と一貫性がある
→ 同様の事例で処分内容に差がない
判定とアクション
- Yesが8〜9個:合法的な解雇に該当する可能性が高い → 手続きへ進む
- Yesが5〜7個:不足項目を補完 → 社労士・弁護士に相談してから進行
- Yesが4個以下:解雇は危険 → 改善指導や配置転換で再度改善機会を与える
実務での使い方
- 解雇稟議書の一部として活用
- 社労士・顧問弁護士との事前相談資料に添付
- 証拠書類とこのチェックリストをセット保管し、法的紛争時に提出可能にする
補足
- このリストは「解雇の必要条件」を簡易確認するものです。最終判断は必ず専門家(社労士・弁護士)と行ってください。
- 特に懲戒解雇は社会的制裁が強いため、慎重さが求められます。
違法とされる可能性が高いケース
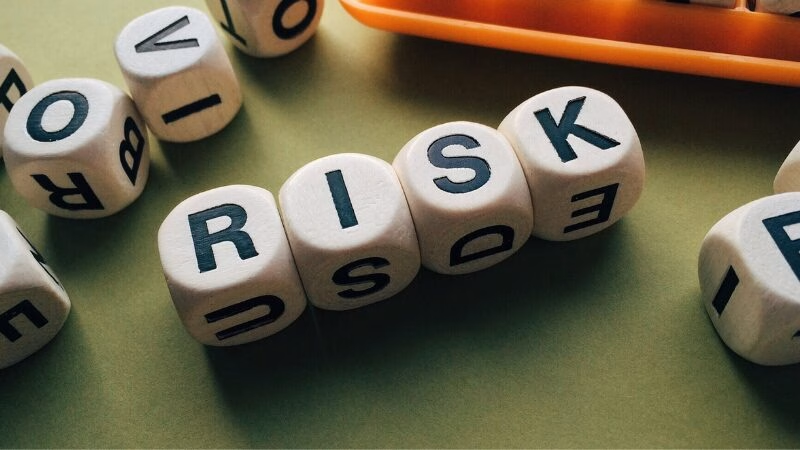
従業員の解雇は、労働契約法第16条により「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方を満たす必要があります。
この要件を欠くと、解雇は無効となり、裁判や労働審判で復職命令や賃金支払いを命じられる可能性が高まります。以下は、特に違法と判断されやすい典型例です。
1. 差別的・報復的な理由による解雇
- 法的根拠:労働基準法第3条、男女雇用機会均等法、労働組合法
- 概要:性別、年齢、国籍、宗教、障害、内部通報や労組活動などを理由とした解雇は、明確に法律で禁止されています。
- 実例:育休復帰直後の女性社員を「もう必要ない」として解雇 → 無効判決。
- 理由:合理的な業務上の必要性がなく、差別的意図が明白。
2. 改善機会を与えず即時解雇
- 法的根拠:労働契約法第16条
- 概要:能力不足や勤務態度不良を理由にする場合でも、研修・指導・配置転換など改善のための措置を複数回(目安3か月以上)行わなければなりません。
- 実例:1回のミスを理由に即日解雇 → 裁判で「改善努力義務違反」と認定。
- 理由:手続的配慮がないと、合理性が認められにくい。
3. 就業規則にない懲戒事由での懲戒解雇
- 法的根拠:労働基準法第89条、労働契約法第15条
- 概要:懲戒解雇は最も重い処分であり、就業規則に明記された事由でのみ可能です。また、処分の重さが行為の重大性と均衡している必要があります。
- 実例:数回の軽微な遅刻を理由に懲戒解雇 → 「量刑不均衡」で無効。
- 理由:就業規則の規定外や過度な処分は違法判断されやすい。
4. 有期契約途中の不当解雇
- 法的根拠:労働契約法第17条
- 概要:有期労働契約は原則として期間満了まで継続する義務があります。契約期間中の解雇は、重大な背信行為や業務不能状態など特別な事由がなければ認められません。
- 実例:契約残り2か月のパート社員を経営不振のみで解雇 → 無効判決。
- 理由:契約期間中は安定した雇用が保護されるため。
5. 解雇予告義務違反
- 法的根拠:労働基準法第20条
- 概要:解雇には30日前の予告または平均賃金30日分の解雇予告手当が必要です。これを怠ると罰則や未払い賃金の支払い命令が下されます。
- 実例:突然の当日解雇で予告も手当もなし → 行政指導+労働審判で支払い命令。
- 理由:予告制度は労働者保護の基本ルールであり、違反は即時に違法。
違法リスクを避けるための3つのヒント
- 就業規則と解雇理由の整合性を必ず確認
- 証拠(記録・書面・証人)を揃えてから着手
- 専門家(社労士・弁護士)による事前チェックを必須化
退職勧奨を行う際の注意点
退職勧奨は、企業が従業員に対して自主的な退職を促す行為です。
解雇と異なり強制力はありませんが、進め方を誤ると「実質的な解雇」とみなされ、労働契約法第16条や判例法理に基づき無効と判断されるリスクがあります。
特に、勧奨の方法が従業員の自由意思を侵害すると、パワハラや脅迫として損害賠償の対象になることもあります。
1. 過度な回数・長時間の説得はNG
- 法的背景:最高裁(東芝柳町工場事件)などでも、繰り返し呼び出す行為は「違法な圧力」と認定。
- NG例:短期間に何度も面談、1回数時間に及ぶ拘束、退職届をその場で書かせる。
- 回避策:必要最低限の回数(目安1〜2回)、面談時間は30〜60分以内に制限。
2. 威圧的・脅迫的発言の禁止
- 禁止発言例:「辞めなければ懲戒解雇だ」「次の職場は見つからない」
- 理由:パワハラ防止法、刑法の脅迫罪のリスク。
- 回避策:事実に基づく業務上の評価と必要性を、冷静かつ客観的に説明。
3. 面談は複数名+記録化
- メリット:後日の「言った・言わない」防止。
- 実務例:人事担当者と上司、または社労士・弁護士が同席。
- 証拠方法:録音(ICレコーダー)、議事録、署名付き面談記録。
4. 合意内容は必ず書面化
- 書面に明記する内容:退職日、退職理由(合意退職)、退職金・未払賃金・有休消化方法、離職票交付時期。
- 理由:口頭合意のみは争いの元。裁判では書面が最重要証拠になる。
5. 条件提示は合理的かつ公平に
- 推奨例:退職金の上乗せ、再就職支援サービス、円満退職証明の発行。
- 理由:条件が一方的に不利だと無効主張や不当労働行為の判断が下される可能性。
- 交渉ポイント:労働者側にとって「残るより退職した方が合理的」と思える条件設計。
6. 全経過の記録保管と相談先案内
- 保管内容:面談日時・参加者・発言内容・提示条件・同意経緯。
- 保存期間:最低3年、できれば5年。
- 相談体制:社内ハラスメント窓口、外部労働相談窓口(労働局など)の案内。
まとめ
退職勧奨は自主的合意の形成が大前提です。
手続を誤れば、「解雇回避」どころか「違法解雇」認定+慰謝料請求に発展します。
安全に進めるためには、
- 記録化
- 第三者同席
- 公平な条件提示
- 専門家(社労士・弁護士)の事前関与
の4点を徹底することが、最も確実なトラブル予防策です。
トラブル事例と防止策
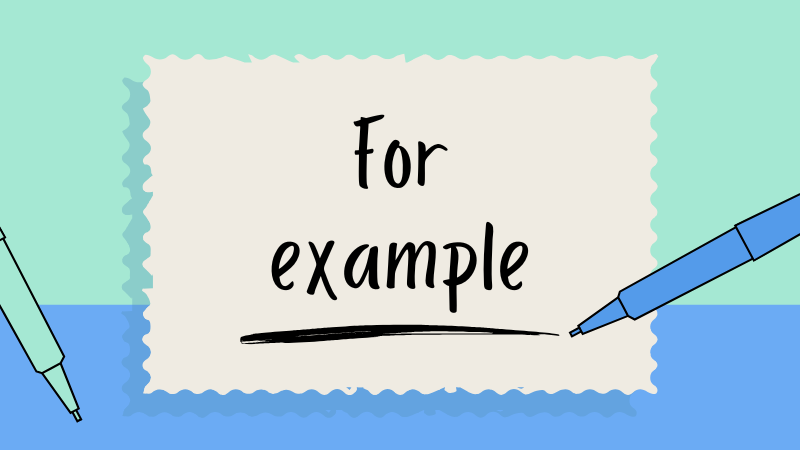
解雇や退職勧奨は、慎重に進めなければ法的トラブルに発展します。
裁判や労働審判では、「客観的証拠があるか」「手続が適正か」が勝敗を大きく左右します。
ここでは、実際の判例や事例をもとに、企業が失敗したケースと、その防止策を解説します。
事例1:証拠不足による解雇無効判決
背景
地方の製造業A社は、ある社員の勤務態度不良と業務ミスを理由に普通解雇を実施。
しかし裁判で求められたのは、「その事実を客観的に裏付ける証拠」でした。
問題点
- 勤怠システムのデータや業務報告書などの一次証拠が存在しなかった
- 口頭注意はしていたが、指導書面・改善計画書が残っていなかった
- 就業規則に定められた懲戒手続を省略していた
判決結果
- 裁判所は「解雇の合理的理由を立証できない」として解雇無効を判断
- 復職命令とあわせて、解雇期間中の未払賃金の全額支払いを命令
防止策
- 勤怠記録・業務ミスの発生日時・具体内容を第三者が確認可能な形で保存
- 能力不足の場合は3か月以上の改善指導+書面記録化を実施
- 就業規則に沿った段階的手続(注意 → 警告 → 解雇)を必ず踏む
事例2:退職勧奨がパワハラ認定
背景
IT企業B社は、業績悪化を理由に一部社員へ退職勧奨を実施。
しかし、上司が短期間に複数回面談し、「残っても評価は下がる」「異動はできない」などの発言を繰り返しました。
問題点
- 短期間に4回以上の面談を実施し、精神的圧迫と受け取られた
- 発言内容が録音されており、威圧的・不安を煽る発言が証拠として残った
- 再就職支援や条件提示など、合理的な選択肢が提示されなかった
判定結果
- 労働審判で「退職の自由意思を侵害した」と認定
- パワハラ+不当な退職強要として慰謝料支払い命令
防止策
- 退職勧奨は最大2回の面談+十分な熟考期間を設定
- 発言は必ず事実に基づき、録音前提で冷静・中立な説明を行う
- 再就職支援や退職金上乗せなど、本人にとって有利な条件を用意
共通の教訓
- 証拠がなければ正当性は立証できない
- 過剰な回数・時間・発言は「自由意思の侵害」と認定されやすい
- 「合理的理由+適正手続+十分な証拠」がそろって初めて合法性が担保される
実務担当者へのアドバイス
- 日常から勤怠・業務・指導の記録化を習慣にする
- 解雇・退職勧奨は社労士・弁護士への事前相談をルール化する
- 社内で「証拠保全マニュアル」を作成しておくと、トラブル時に強い防御になる
解雇後に従業員から訴えられた場合の対応
解雇を行った後、従業員から「不当解雇だ」として労働審判や裁判を起こされるケースは珍しくありません。
労働契約法第16条は「解雇権の濫用は無効」と定めており、解雇後も企業側に立証責任が課せられます。
このとき、勝敗を大きく左右するのは証拠の質と初動対応の速さです。
【初動対応】発生から24時間以内に行うべきこと
- 全証拠の即時確保
- 勤怠データ、評価表、業務ミスの報告書、注意・警告書、就業規則、雇用契約書
- 上司・人事・同僚とのメール、チャット履歴、面談録音
- デジタルデータは削除・改ざんの痕跡が残らない形で保管
- 事実関係の時系列整理
- 「発生→注意→改善指導→解雇通知」までの流れを日付順にメモ化
- 誰が関与したか、どの証拠がどの場面を裏付けるかを一覧化
【専門家対応】72時間以内に着手
- 弁護士・社労士への即時相談
- 証拠の有効性、主張の組み立て方、想定される相手側の反論を事前に把握
- 書面提出期限や労働審判のスケジュールを逆算し、準備計画を立てる
- 勝訴確率の評価
- 「勝訴見込み70%以上なら継続、50%以下なら和解も選択肢」にする企業も多い
【手続別の対応ポイント】
- 労働審判(最短1〜2か月で結論)
- 3回以内で審理終了のため、初回期日までに証拠を全て提出する必要あり
- 証拠が出揃っていない状態で臨むと、その時点で不利になる
- 民事裁判
- 長期化(半年〜数年)しやすく、地位保全仮処分で給与仮払い命令が出る可能性
- 労働基準監督署申告
- 行政指導→是正勧告→企業名公表のリスクあり
- 手続自体は労基署が主導するため、記録の一貫性が特に重要
【和解判断】企業防衛の視点
- 和解のメリット
- 訴訟長期化による費用・時間・社内士気低下を回避
- メディア露出やSNS拡散などの風評被害リスク低減
- 和解時の必須条件
- 守秘義務条項
- 今後の請求放棄
- 社内外への発表方法の合意
【社内外の影響管理】
- 社内:人事・役員のみ詳細共有、不要な噂防止
- 社外:取引先・顧客からの問い合わせ対応マニュアルを作成
- 広報:必要に応じて危機管理広報を専門家と準備
まとめ
- 解雇後は「終わり」ではなく「法的リスクの始まり」と捉える
- 勝つための3原則は
- 即時証拠保全
- 初動72時間以内の専門家関与
- 手続と証拠の一貫性確保
- これらを平時から準備しておけば、訴えられても慌てず企業防衛が可能になる
専門家を活用するメリット

解雇や退職勧奨は、企業の人事判断の中でも最も慎重さが求められる場面です。
一度でも「不当解雇」や「パワハラ」として争われれば、金銭的損失・時間的ロス・企業イメージの低下が同時に発生します。
こうしたリスクを事前に回避するために有効なのが、弁護士や社会保険労務士(社労士)といった専門家の活用です。
1. 法的リスクを事前に封じ込める
- 最新の労働契約法・労働基準法・均等法・判例を踏まえて、合法的な手続を設計
- 「この解雇理由で勝てるか」を着手前に法的観点から判定
- 過去の判例を参照し、同じ失敗を回避できる
例:勤怠不良による解雇を進める際、過去に同様の事例で無効になったケースを参考に、改善指導期間を3か月確保
2. 裁判で通用する証拠の整備
- 労働審判や裁判で有効とされる証拠形式を熟知
- 口頭注意を「指導書」に、勤怠記録を「改ざん不可形式」に整理するなど、証拠の立証力を最大化
- 面談録音・議事録・メール履歴など、どこを押さえれば勝てるかを明確に指示してもらえる
3. 時間・労力・精神的負担の削減
- 専門家が書面作成・相手方対応を代行
- 人事担当者は本業や他の従業員対応に集中できる
- 交渉が長引くほど企業内部が疲弊するため、短期決着は最大の防御策
4. 有利な交渉展開が可能
- 弁護士名での通知は、相手に「本気度」と「法的裏付け」を伝える効果
- 和解交渉でも、慰謝料や和解金を相場内または相場以下に抑えられる
- 感情的対立を避け、冷静かつ事実ベースの話し合いに持ち込める
5. 企業ブランド・信用の保護
- 法的に適正な手続を踏むことで、労働者や取引先からの信頼を維持
- 「あの会社はルールを守る」という評判は採用や営業にもプラス
- 不当解雇やハラスメント報道によるブランド毀損リスクを事前に遮断
実務的アドバイス
- 「トラブルが起きてから」ではなく「起きる前」に相談する方がコストは圧倒的に安い
- 顧問契約にしておけば、スポット相談より1回あたりの費用が下がり、日常的な労務判断も即日確認可能
- 社労士は手続や書類整備、弁護士は紛争解決と役割が異なるため、両者を併用すると万全
まとめ
専門家の活用は、単なるトラブル対応ではなく「予防医療」に近い効果があります。
法的な正しさと手続の適正さを担保しながら、企業の時間・コスト・信用を守ることが可能です。
特に中小企業では人事労務の専門部署がないことが多く、顧問弁護士・顧問社労士の存在はリスクマネジメントの必須装備といえます。
まとめ|「辞めさせる」ではなく「正しい手続きを踏む」
解雇は、単なる人員整理ではなく、企業の信頼・法的安全性・組織文化すべてに直結する重大な経営判断です。
短期的な感情や場当たり的対応で進めると、不当解雇・パワハラ認定・損害賠償請求といった高リスクの事態を招きます。
正しい手続が「企業を守る盾」になる
- 解雇理由や証拠が不十分なまま進めれば、たとえ事実があっても裁判では不利になります
- 就業規則や雇用契約書に基づき、改善指導→記録→配置転換→警告→解雇通知の順序を踏むことで、法的有効性が担保されます
- 専門家の助言は、制度設計から証拠の整備、交渉戦略まで企業を守るための保険です
「解雇」という判断を下す前の最終チェック
- 法的根拠は明確か(就業規則・契約書・法律上の要件を満たすか)
- 改善機会は十分与えたか(指導・研修・配置転換・警告書発行)
- 証拠は揃っているか(勤怠記録・評価・指導履歴・面談録音など)
- 専門家の確認を受けたか(弁護士・社労士の事前チェック)
- 社内・社外への影響を想定したか(残る従業員の士気・取引先への信用)
経営判断の質が組織の未来を決める
適正な手続きを踏むことは、単に法律を守るためだけではありません。
「公正な判断をする企業」という評価は、採用や取引にも好影響を与えます。
逆に、感情的な解雇は短期的な問題解決に見えても、長期的には人材離れ・信用低下という形で返ってきます。
次のアクション
- 自社の就業規則・解雇手続の流れを棚卸し
- トラブル発生時は初期段階で専門家に相談
- 社内に「証拠を残す」文化を定着させる
「辞めさせる」ではなく、「正しい手続きを踏む」
これが中小企業にとって、法的リスクを最小化し、信頼を守りながら組織を健全に保つ唯一の道です。
この他の記事では、採用や財務に特化した記事も掲載しています。併せて参考にしてください。
採用は委託する時代?採用委託(BPO)とは?メリットと費用相場を説明
【2025年版】中小企業が絶対に押さえたい経費削減の実践ポイント
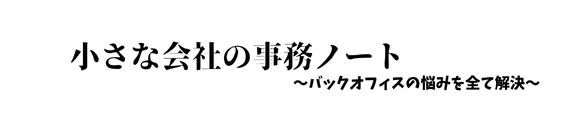
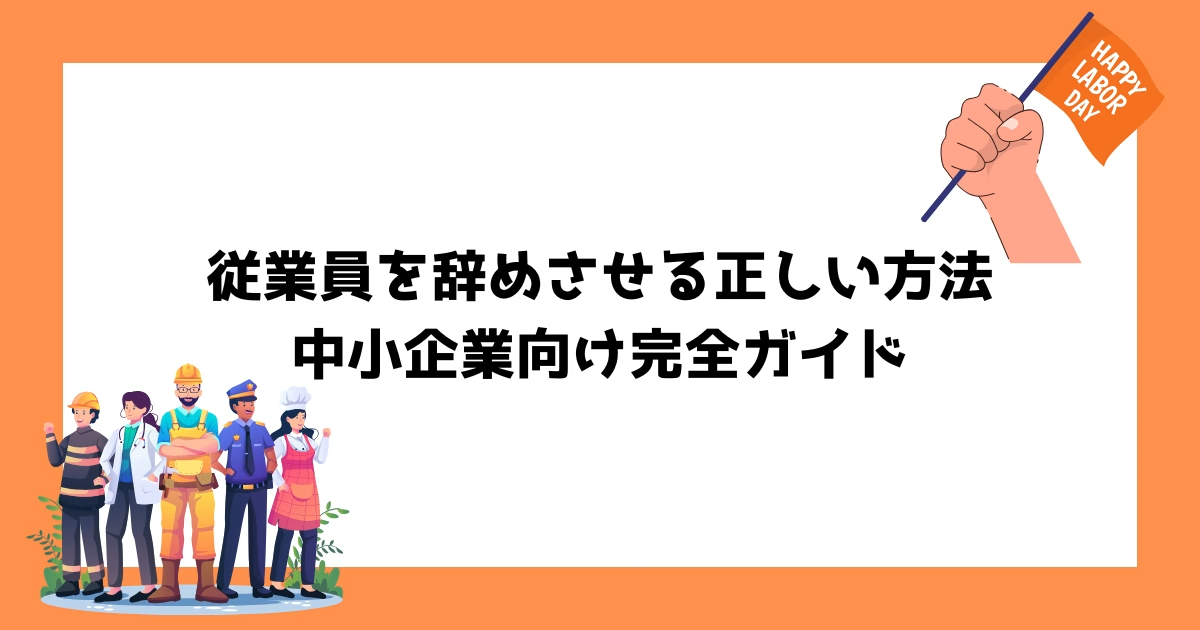
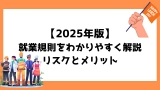



コメント