「うちなんて人数少ないし、社労士はいらないかな」
このように考えられている中小企業も少なくはないのでしょうか。
私自身、就業規則など労務に関する勉強をし始めたばかりにころは、社労士はどちらかというと規模感の大きい企業のためにいる方達だというイメージを持っていました。
しかし、実際に現場で中小企業の社長や事務の方々と話をする中で、むしろ中小企業、人数の少ない企業ほど社労士と契約して、本業に集中できる環境を作るべきであるという考えに変わってきました。
今回は、社労士と顧問契約をするメリットをお伝えしていきます。
当然自社内で全てを内製化していくのも、メリットはたくさんあると思います。今回お伝えする、契約時のメリットと比較検討して自社に合った方法を見つけて行ってもらえればと思います。
忙しい方はぜひ太字部分だけでも読んでみてください。
中小企業における社労士業務とは

従業員数10人未満
主な業務・役割
- 入退社手続き(社会保険・雇用保険の取得・喪失)
- 給与計算や賃金台帳・勤怠管理のサポート
- 年金事務所・ハローワークへの各種届出代行
- 労働契約書や雇用契約書の整備アドバイス
- 最低限の就業規則作成・簡単な労使トラブル相談
ポイント
- 「最低限の法令順守」のための基礎的サポートが中心。
- 事務担当者(経理・奥様など)が兼任している場合が多いが、イレギュラー時だけスポットで社労士を頼るケースも。
2. 従業員数10〜30人
主な業務・役割
- 上記に加え、
- 助成金・補助金の案内や申請サポート
- 就業規則の定期見直し・規程類の整備
- 時間外労働・36協定の提出・管理
- 定期的な給与計算代行や勤怠集計業務の受託
- 残業や有給休暇管理のルール策定
- 定期的な労働法改正への対応アドバイス
- 簡単な労使トラブル・解雇・未払い残業代などの相談窓口
ポイント
- トラブルや法令違反が発生しやすい人数帯。
- 「自己流」の限界が来やすいので、月額顧問契約が多くなる。
- 定期的なチェックやアドバイス、何かあったときすぐ相談できる存在としての役割が大きい。
3. 従業員数31〜50人
主な業務・役割
- 上記に加え、
- 社内研修・ハラスメント対策の導入
- 評価制度・人事制度の設計や運用支援
- 健康診断やストレスチェックの実施管理
- 監督署や年金事務所の調査・立入対応
- 複数拠点・多様な雇用形態への対応
- より高度な労務管理(パート・派遣・外国人雇用の手続き等)
- 万が一のトラブル時(訴訟・労基署指導等)への初動アドバイス
ポイント
- 「組織的な人事・労務管理」が必要になり始める人数帯。
- 労務管理の質や体制が問われる。
- 社長だけでなく、人事担当者や管理職も社労士と連携しながら制度運用。
4. 従業員数50人以上
主な業務・役割
- 上記すべてに加え、
- 労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届など複雑な手続きが大規模化
- 産業医選任や衛生委員会設置義務(常時50人以上)対応
- コンプライアンス・リスクマネジメント対応の強化
- 多拠点・複雑な組織体制への総合的な労務コンサルティング
- 退職・解雇等の高度なトラブル対応、助成金申請の複雑化対応
- 人事制度・評価制度・賃金制度の本格的導入・見直し
- 労働時間管理やメンタルヘルス対策の運用サポート
ポイント
- 法定義務・書類作成・人事制度運用が「経営課題」になる規模。
- 社労士が“顧問”だけでなくパートナーとして関与することが増える。
- 社内担当者と分業・連携体制が必要。
社労士と顧問契約するメリット
1.手間と時間の大幅削減
1-1. 面倒な手続き・書類作成のアウトソーシングができる
社会保険や労働保険の加入・喪失、各種給付申請、年度更新や算定基礎届など、膨大で複雑な事務手続きをすべてプロに任せることができ、自社での記入や提出の手間が大幅に減ります。
1-2. 法改正や制度変更への対応が不要になる
毎年のように変わる労働法や社会保険制度について、自分で調べて適切に対応する手間が不要。社労士が最新情報をもとに必要なアドバイスや手続きを自動で案内してくれます。
1-3. トラブル対応・相談の即時化
労務トラブル(解雇・残業・ハラスメント等)が起きた時、ゼロから調べたり弁護士に相談する時間が不要。社労士へすぐに相談でき、対応策を最短で得られます。
1-4. 書類のミス・再提出が激減
慣れない担当者による記入ミスや提出漏れがなくなり、役所からの問い合わせや差し戻し対応にかかる時間的ロスを防げます。
1-5. 助成金・補助金の申請も効率化
自社だけでは気付きにくい助成金情報を受け取れ、申請書類もサポートしてもらえるため、調べたり書類を作る時間を大幅に削減できます。
2.労務トラブルの予防と迅速対応
2-1. 就業規則や労使協定の整備でトラブルを未然に防げる
社労士が最新の法改正や判例をふまえて就業規則・労使協定を整備してくれるため、「曖昧なルール」が原因のトラブルを防げます。
2-2. 日々の労務相談が気軽にできる
ちょっとした疑問(残業・有休・退職時の対応など)もすぐに相談できるため、早い段階でリスクの芽を摘むことができます。
2-3. 問題社員やハラスメント対応をアドバイス
解雇や懲戒、パワハラ・セクハラなどの問題発生時も、法的に正しい対応方法をその場でアドバイスしてもらえるので、対応ミスによるトラブル拡大を防げます。
2-4. 行政対応や調査も安心
労働基準監督署や年金事務所からの調査・是正勧告が来た際も、社労士が立ち会いや対応方法をサポートしてくれるため、不安や手間が最小限です。
2-5. トラブル発生時も「すぐに動ける」
万が一トラブルが発生した場合も、顧問社労士が既に会社の状況を把握しているので、ゼロから説明する必要がなく、スピーディーに対処できます。
3.助成金・補助金の情報と申請サポート
3-1. 制度の最新情報をプロがキャッチしてくれる
助成金や補助金は毎年条件や内容が変わりやすく、経営者自身が常にチェックするのは困難です。社労士は最新の国・自治体の制度に精通しているため、取りこぼしなく案内してくれます。
3-2. 自社に合った制度を選定・提案してもらえる
社労士は会社の雇用状況や経営計画を把握した上で、該当する助成金・補助金を「選別」して具体的に教えてくれるので、無駄なリサーチや不適切な申請を減らせます。
3-3. 複雑な申請書類の作成・提出をサポート
助成金申請は書類作成や証拠書類の準備が面倒ですが、社労士がフォーマットや記載方法、添付書類の準備までトータルでサポートしてくれるため、書類不備や差し戻しリスクも下げられます。
3-4. 申請後のフォローや追加対応も代行
申請後の審査対応や追加提出書類、必要に応じた修正も社労士が迅速に対応してくれるので、経営者の負担が大幅に軽減します。
3-5. 不正受給リスクや要件ミスを防げる
知らず知らずのうちに「要件違反」や「記載ミス」で返還を求められるケースも。社労士のチェックがあれば制度に沿った正しい運用ができ、トラブル予防にもなります。
4.就業規則や社内ルールの整備・改訂
4-1. 法改正や判例に即したルールが作れる
社労士は最新の労働法や判例に常にアンテナを張っています。これにより、法律違反や古い内容を防ぎ、安心して使える就業規則を作成・改訂してもらえます。
4-2. トラブルの芽を事前に摘むルール設計ができる
解雇・休職・残業・ハラスメントなどの“曖昧さ”があると労務トラブルに直結しがちです。社労士なら実務でよくあるケースを踏まえた、抜けや漏れのない規則を整備できます。
4-3. 自社の実情やニーズに合わせたオーダーメイド設計が可能
ネットや本のひな形ではなく、業種や働き方、自社の文化に合わせた「会社らしいルール」を一緒に考えてもらえます。現場の混乱や不満も防ぎやすいです。
4-4. 社員説明や運用サポートまで一括で相談できる
規則の作成だけでなく、社員説明会や質疑応答のサポート、規則の運用アドバイスも受けられるので、導入後も安心です。
4-5. 定期的な見直し・アップデートも任せられる
法改正や働き方の変化に合わせて、定期的な規則改訂・アドバイスがもらえます。放置して気づいたら違法を防げるのは大きなメリットです。
5.採用から退職まで一貫サポート
5-1. 採用時の労働条件や雇用契約書の作成・チェックが安心
社労士が入ることで、求人票や雇用契約書の内容が最新の法令に沿っているか確認・作成できます。後から「契約内容に不備があった…」といったトラブルを未然に防げます。
5-2. 入社手続き(社会保険・雇用保険等)の事務がスムーズ
社員が入社したときの各種手続き(社会保険・雇用保険・労災など)も社労士が的確にサポートしてくれるので、抜け漏れや手続きミスが起こりにくくなります。
5-3. 就業中の労務管理や働き方相談もワンストップ
勤務時間管理や残業、育休・産休、ハラスメント、メンタルヘルスなど日々の労務トラブルの予防と相談も、専門家に一貫して相談できる安心感があります。
5-4. 退職時の書類・手続き・トラブル対応もプロが対応
退職・解雇・雇用保険の手続きなど、トラブルが起きやすい場面も社労士が対応。退職勧奨や離職票の発行、残業代・有休消化などの対応も的確です。
5-5. 社員のライフステージ全体をカバーできる
採用から退職、育休・産休・復帰、病気休職など、社員の人生のあらゆる場面で必要な労務サポートを一社でまとめて任せられるため、経営者や総務担当の負担を大きく減らせます。
6.経営者・担当者の“相談役”になる
6-1. 労務や人事の専門知識を“すぐに聞ける安心感”
法律や制度は複雑で毎年のように変わりますが、分からないことや不安なことをその都度プロに相談できるため、経営判断に迷いがなくなります。
6-2. トラブルの“早期発見・未然防止”ができる
「こんな時どうしたら…?」と小さな相談を気軽にできることで、問題が大きくなる前に対策を打てます。早期対応によって大きな損害を防げることも。
6-3. 社内での決定事項や運用方針に“自信が持てる”
例えば「就業規則をこう変えたい」「新しい制度を導入したい」というとき、社労士の助言があれば法律違反や従業員トラブルを避けつつ、適切に進めることができます。
6-4. “経営の視点”も交えた客観的なアドバイスがもらえる
単なる手続きだけでなく、「今の人事制度は会社の成長に合っているか?」など、会社の規模や方針を考慮した実践的なアドバイスが受けられます。
6-5. “第三者の立場”だからこそ話しやすい・相談しやすい
社内では相談しにくい悩みや、利害関係が絡むデリケートな話題も、外部の専門家という立場だからこそ本音で相談できます。経営者や担当者の心の負担も軽減されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
労務の専門家である、社労士と顧問契約をすることで、事前にリスク対策をすることができ、あらゆるトラブルを未然に防ぐことができます。
また、専門家が身近にいる。相談できる人がいるという心理的安心はかなり大きいものではないでしょうか。
今回の記事を参考に社労士の先生との付き合い方を検討してもらえると嬉しいです。
またこの他の記事では、いまさら専門家に相談しにくいような労務や財務に関する基礎の基礎を情報発信しています。ぜひ参考にしてみてください。
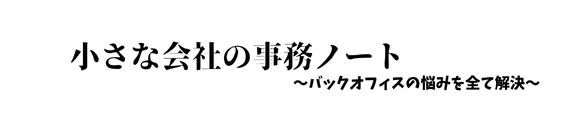
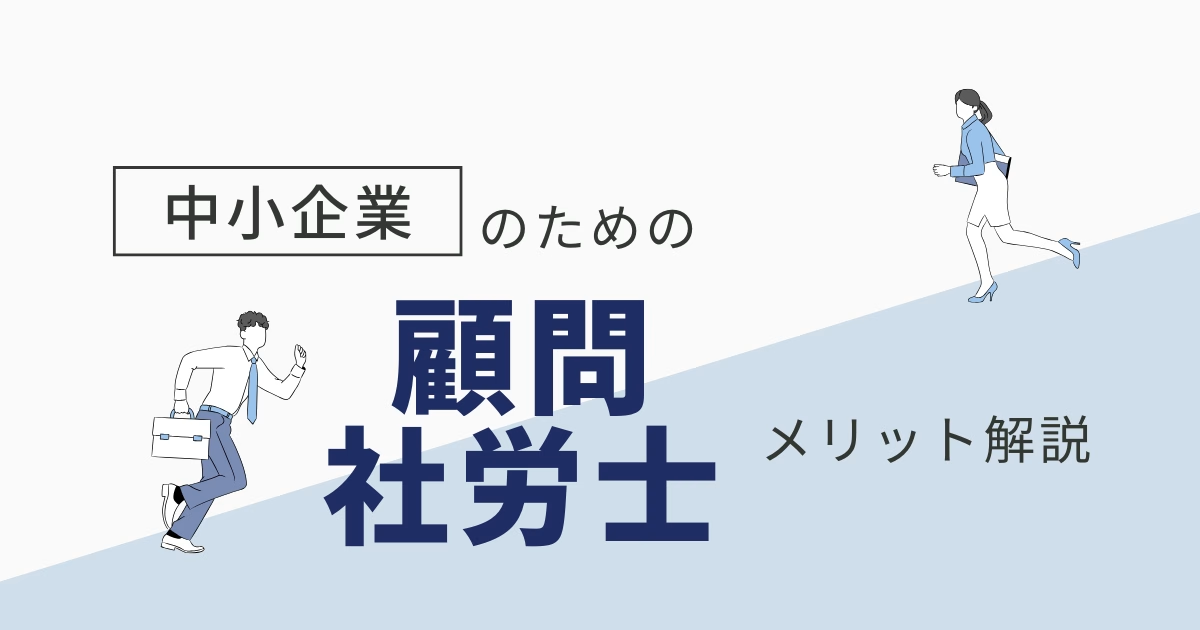


コメント