「やばい、とんでもないミスをした!」「やばい!ミスってクビになりそう…」このブログを読んでいるあなたは今、そんな不安で頭が真っ白になっていませんか?
経理担当者なら誰しも一度はヒヤッとした経験があるはずです。たった一度の大きなミスで「明日から会社に行けないかも」と不安になるのは、決してあなただけではありません。
この記事では、「経理でやってはいけないミス」をしてしまったときでも、クビを回避し、信頼を取り戻すための具体的な対処法を分かりやすく解説します。
「どう謝ればいいの?」「再発防止策は?」「職場への報告は?」など、今まさに困っている人が今日から使える実践的なノウハウが満載です。
焦らずに正しく対応すれば、大きなミスでもリカバリーできます。実際に多くの経理担当者が、冷静な対処と誠実な行動でクビや評価ダウンを回避しています。
この記事を読めば、ミス後の一手が変わり、きっとあなたの「再起」が叶います。ぜひ参考にしてください。
なぜミスが起こる?

経理業務は日々のルーティンワークが多い反面、数字の一桁違いや仕訳の記入ミス一つで大きな問題につながります。
ミスが起きる背景には、「作業のマンネリ化」「締切や繁忙期による焦り」「確認不足」「業務量の多さ」「人手不足による多重業務」などが挙げられます。
また、経理ソフトやシステムの入力ミス、伝票の読み違い、口頭指示による誤認などヒューマンエラーはどんなベテランでも避けきれません。
「自分だけ…」と責めるよりも、環境や仕組みに原因があることを理解しましょう。
ミスが起きたらまずすること

大きなミスをした直後ほど、冷静さを失いがちです。
まずは落ち着き、「どんなミスを、どの範囲で、いつ起こしたのか」を正確に把握しましょう。
次に、事実を隠さず、すぐに上司や関係者に報告することが最優先です。「報告が遅れるほどダメージが大きくなる」ケースが多いため、素直に謝罪し、自分の責任を明確に伝える姿勢が信頼回復の第一歩となります。
その後、ミスによる影響範囲を整理し、必要であれば「再発防止策」を提案しましょう。感情的になりすぎず、事実と向き合うことが重要です。
ミス回避方法とは?おすすめ5選

ダブルチェック体制を作る
経理業務は数字の正確さが求められる反面、人間の注意力だけに頼るとどうしてもミスが発生します。特に中小企業では、担当者が一人で複数業務を兼任しているケースも多く、確認不足や思い込みによる誤りが起こりやすいのが現実です。
ダブルチェック体制を作ることで、他人の目による客観的な確認が加わり、単純な入力ミスや記入漏れ、伝票の転記ミスなどを早期に発見できます。チェックする人と作業する人を分けることで、「これくらいは大丈夫だろう」という油断も防げます。
また、万が一ミスが発覚した際も、「どこで誰がチェックしたか」が明確になるため、原因分析や再発防止策の立案がしやすくなります。経理の信頼性は、社内外の信用にも直結します。小規模な会社でも、たとえば週1回だけでも複数人で見直す仕組みを取り入れることで、ヒューマンエラーによるトラブルを大きく減らすことができます。
属人化しやすい中小企業の経理現場だからこそ、ダブルチェック体制の導入は、日々の安心とミスの抑止力につながるのです。
チェックリストやルールを明文化する
経理業務は複雑な手順や細かいルールが多く、担当者によって「やり方」や「意識するポイント」がバラバラになりがちです。チェックリストやルールを明文化することは、そうした属人的な業務を標準化し、誰が担当しても一定レベルの品質を保てる状態を作るうえで欠かせません。
たとえば「仕訳入力前に請求書原本と照合する」「振込前は必ず金額と口座を二重確認する」など、細かな手順を明文化することで、手順の抜けや思い込みによるミスを防ぐことができます。
また、新人や異動者がスムーズに業務を引き継げるため、急な人員変更が発生してもリスクを最小限に抑えられます。チェックリストは“慣れ”による確認漏れも防ぎ、作業終了後に「全部できているか」を客観的に振り返るツールとしても有効です。
経理は“正確さが当たり前”と思われがちですが、現場には小さなミスがつきものです。だからこそ、明文化されたルールとチェックリストで日常の“うっかり”を仕組みでカバーすることが、ミスゼロ経理への第一歩となります。
「忙しい時ほどゆっくり」を意識する
経理の繁忙期や月末月初には、締め切りや突発的な対応が重なり、どうしても「急いで処理しなければ」と気持ちが焦りがちです。しかし、焦りや急ぎ作業こそが最も大きなミスの原因になります。忙しいときこそ「一度深呼吸して、作業スピードを落とす」という意識がとても重要です。
実際、経理のヒューマンエラーの多くは“うっかり”や“確認漏れ”から生じています。余裕がない時ほど、確認を省略したり、チェックリストを飛ばしたりすることが多く、それが後々大きなトラブルにつながります。「忙しいからこそ、ゆっくり丁寧に」をチーム全体の合言葉にすることで、無駄な焦りを抑え、落ち着いた確認作業を徹底できます。
実務では、「この作業だけは絶対に立ち止まって見直す」「疲れてきたらいったん席を立つ」など、自分なりの“落ち着くスイッチ”を作るのも効果的です。結果的に、忙しい時ほどミスが減り、最終的な手戻りや信用損失のリスクも大幅に下げることができます。
定期的な業務改善を行う
中小企業の経理業務は、「昔からのやり方」や「誰かが作ったルール」がそのまま温存されているケースが多く、非効率な作業や二重チェック、無駄な手順が積み重なっていることも珍しくありません。こうした“形骸化した業務”がミスや確認漏れ、負担増加の温床になります。定期的に業務フローやルールを見直し、「本当にこの手順は必要か?」「もっと簡略化できないか?」と問い直すことで、現場に合った効率的な仕組みにアップデートできます。
たとえば、紙で管理していた帳票を電子化したり、担当者の負担を減らすための自動集計ツールを導入したりするのも有効です。業務改善には現場担当者の声やアイデアが欠かせません。定期的にミーティングを設けて、問題点を洗い出し、小さな改善を積み重ねていくことが大きな成果につながります。
経理は「正確さ」と「スピード」を両立させる仕事だからこそ、時代や現場の変化に合わせて業務改善を続けることで、ミスの温床を減らし、より強い経理体制を作ることができます。
システム化する
経理ミスの多くは「手作業」による入力間違いや計算ミス、記録の漏れから発生します。これを根本的に防ぐ手段が「システム化」です。会計ソフトや経費精算システムを導入することで、伝票の自動転記や金額計算、承認フローの自動化など、ヒューマンエラーの入り込む余地を大幅に減らせます。
特に中小企業は少人数体制で経理を回していることが多く、システム化によって業務の効率化と標準化を同時に実現できます。
また、システムには履歴管理やエラーチェック機能が備わっており、入力ミスが発生した場合でもすぐにアラートを出してくれるため、「うっかり」の早期発見・是正につながります。最近はクラウド型サービスも普及し、初期費用や運用コストを抑えて手軽に導入できるものも多いです。
「紙から脱却して、数字の管理を“見える化”したい」「どんな人が担当してもミスなく処理できる仕組みを作りたい」そんな現場こそ、システム化が最大の武器になります。人手不足や業務の属人化が課題になりがちな中小企業の経理現場にとって、システム化はミスゼロ経理への最短ルートと言えるでしょう。
おすすめシステムはこちら
経理の効率化・ミス削減を本気で目指すなら、クラウド会計ソフト「マネーフォワードクラウド」が断然おすすめです。
◆作業時間の大幅削減!
クレジットカードや銀行口座、ECサイトなどと自動連携し、入出金や決済データを自動で取得・仕訳。
手入力や転記の手間、単純な打ち間違いによるミスも大きく減らせるため、会計業務にかかる時間もコストも圧倒的に削減できます。
そのぶん、本来注力すべき業務に集中できる環境を実現します。
◆連携できるサービスが圧倒的に豊富!
会計処理だけでなく、給与計算や勤怠管理などバックオフィス全般をカバーしてくれます。
管理業務の一元化ができ、会社の成長に合わせて必要な機能だけを自由に選べます。
幅広い業種・規模の中小企業で導入が進んでいる理由はこの「拡張性の高さ」にあります。
◆法改正にもスピード対応!
「電子帳簿保存法」「インボイス制度」など、最新の法改正にもいち早く対応。
証憑の自動分類や記録、消費税対応など複雑化する税務処理もラクにこなせます。
法令対応で悩んでいる経理担当者にも心強い味方です。
業務効率も法対応も妥協したくない!そんなあなたは「マネーフォワードクラウド」を試してみてください。
まとめ
今回は経理業務でミスが起きた際にどうしたら良いのか、ミスを回避するにはどうしたら良いのかをまとめていきました。
仕事をする上でミスを0にすることはできません。しかし、確実にミスを減らすこと、ミスが起きてからリカバリーすることは可能です。
さまざまな方法でミスが起きない仕組みづくりをして、安心して働ける環境づくりをしていきましょう。
またこの他の記事では、経理閑散期の過ごし方や、決算書の見方などをまとめています。併せて参考にしてみてください。
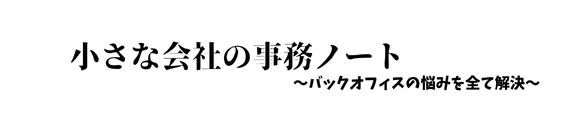
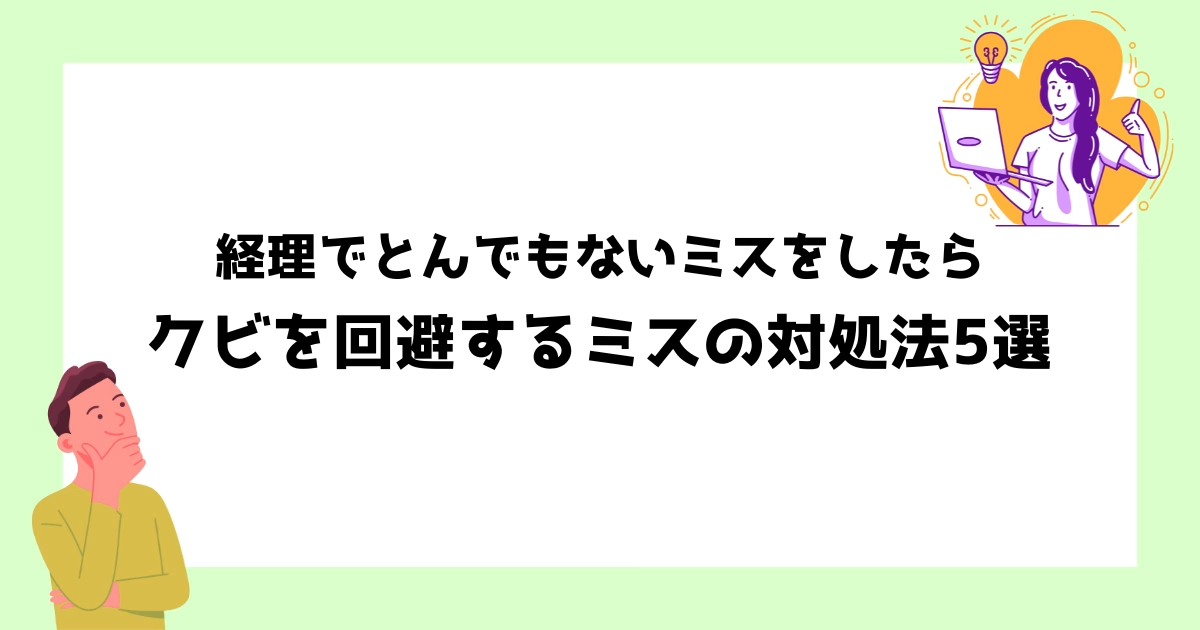
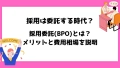

コメント