これまで数百社の中小企業様を訪問してきましたが、従業員数10人未満の企業様では、就業規則が準備されていない場面に多く遭遇してきました。
労働基準法では第89条で、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」としているため、従業員数10人未満であれば作成義務はありません。
しかし、何かトラブルが起きた際に会社のルールとして確認されるのは従業員数が何名であっても就業規則です。
どうしても就業規則がない場合は、言った・言わないの話になったり、感情での判断になったりするケースが多いです。
そのため、リスク管理の観点からは1人でも人を採用する場合は就業規則の整備をお薦めしています。
このブログでは、これまで数多くの企業から聞いた「従業員数が10人未満で就業規則がない場合のリスク」「アットホーム・家族感の罠」をまとめています。
ぜひ従業員数に関わらず、しっかりとした労務整備を行い安全な企業経営を行ってください。
10人未満だからこそ!就業規則がない場合のリスク5選
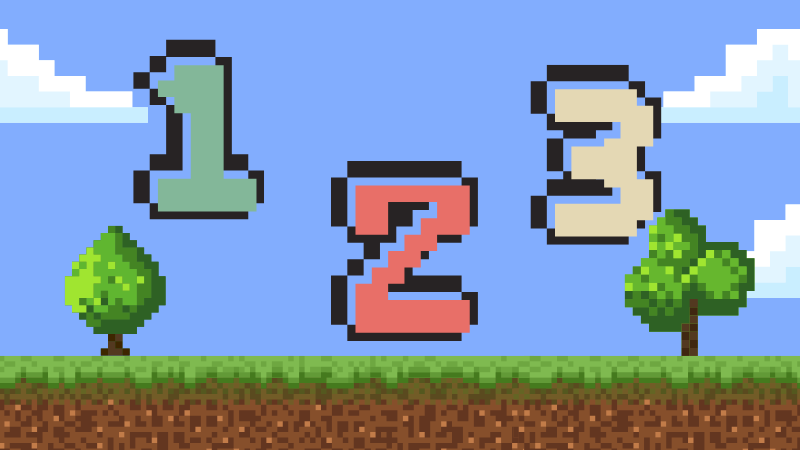
“家族的経営”でも感情トラブルが一瞬で大ごとに
小規模な会社では、社長や従業員の距離が近く、家族のような雰囲気でお仕事をされていることが多いですよね。
それゆえに「ちょっとしたミスや遅刻もお互い様」「空気を読んでカバーしあう」「細かいルールを決めなくても困らない」と考えがちです。
しかし場合によっては、この「家族的な雰囲気」こそが、大きなトラブルの火種になることもあります。
例えば、普段はなんとなくで済んでいた遅刻や早退が、ある日突然「なんであの人だけ許されるの?」という不満につながったり、同じ失敗でも対応が違うと「えこひいきだ!」と感じる人が現れたりします。
人数が少ないからこそ、一人の不満や誤解が一気に会社全体に広がりやすく、場合によっては仲間割れや退職の連鎖につながることもあります。
また、親しさからあうんの呼吸で動いているうちは良くても、途中で新しい人が入った時や、家族以外のメンバーが増えた時に「そんなの聞いてない」「前の人には許されていたのに」といったズレや摩擦が生じる危険性があります。
結局、ルールがないままでは、社長や古参メンバーの主観で物事が決まってしまうケースが多いです。トラブルが起きてから「言った・言わない」で揉めたり、話し合いがこじれて大切なスタッフが離れてしまうケースも珍しくありません。
だからこそ、小規模な会社だからこそ家族的経営だからと油断せず、トラブルを未然に防ぐためにも最低限のルール(就業規則)を用意することが大切です。
“暗黙の了解”の崩壊で一気に不満が噴出
従業員10人未満の会社では、「うちはルールよりも空気感」「細かい決まりを作らなくても、なんとなく分かり合える」と考えがちです。この考えも素敵で大事な考えだと思います。
実際、長く一緒に働くメンバー同士なら「昼休憩のタイミング」「遅刻や早退の扱い」「ちょっとした用事での外出」なども、特に明文化せず“暗黙の了解”で済ませていることが多いですよね。
しかし、この“暗黙の了解”はいつまでも安定して続くものではありません。
例えば、ある日突然新しい人が入ってきたり、今まで何も言わなかった人がふとしたきっかけで「なんであの人だけ許されるの?」と不満を感じたり…。それまで当たり前だった「みんなの常識」が通じなくなる瞬間が必ず訪れます。
こうしたタイミングで、ひとたび“暗黙の了解”が崩れると、「どうして自分だけ注意されたのか」「前はOKだったのに、急にダメと言われた」といった不公平感や不信感が一気に広がりやすくなります。もともとルールがはっきりしていない分、「社長の気分次第で変わるのか?」と疑心暗鬼になることもあります。
人数が少ないからこそ、ちょっとしたズレや不満が“噴出”しやすく、それが職場の空気や人間関係の悪化、時には退職者の増加に直結してしまうケースも珍しくありませんでした。
だからこそ、小規模な会社でもなんとなくに頼らず、誰が読んでもわかる明確なルール(就業規則)を作ることが、平和な職場づくりの一歩となります。
法違反に気づかないリスクが大きい
従業員が10人未満の会社では、「大きな会社ほど厳しく見られないだろう」「昔からこうやっているし大丈夫」といった思い込みがありがちです。
しかし実際は、企業規模に関係なく、労働基準法や社会保険関連の法律はすべての事業所に同じように適用されます。
特に小規模企業では、経理や労務担当を社長や家族、事務員の方が兼任しているケースが多く、日々の業務に追われて最新の法改正や細かな労務ルールまで把握しきれていないことも珍しくありません。むしろ把握できなくて当然です。
「有給休暇をきちんと与えていない」「残業代の計算方法が古いまま」「未成年者や外国人の雇用に特別な配慮が必要と知らなかった」など、本人に悪気がなくても気づかないうちに法律違反という状態が起きやすいのです。
この「気づかない法違反」は、トラブルのきっかけや労働基準監督署からの指導につながります。最悪の場合、賃金の遡及支払いや是正勧告、SNSや口コミでの会社のイメージダウンまで発展することもあります。
規模が小さい会社ほど「法令遵守」を仕組みとして明確にしないと、知らないうちに大きなリスクを抱えてしまうのが現実です。
就業規則の整備や定期的な見直しは、こうした“見えないリスク”を防ぐためにも非常に重要な役割を持っています。
“採用・解雇”が超リスキー
従業員が10人未満の小規模企業では、採用も解雇も「家族的な雰囲気だから何とかなるだろう」とつい軽く考えがちです。
しかし、人数が少ないからこそ、一人ひとりの存在感や影響力が大きく、採用や解雇の判断ミスが会社全体に直結するリスクが非常に高くなります。
まず採用についてですが、「知り合いだから」「頼まれたから」という理由で曖昧に雇い入れると、労働条件が口約束のまま進んでしまい、後になって「聞いていた話と違う」「条件が不明確」とトラブルに発展することがよくあります。
就業規則がない場合、誰に何をどう伝えているかも曖昧になりがちで、不公平感や不満が出やすくなります。
一方、解雇についても大きなリスクがあります。小さな会社では、合わない人材やパフォーマンスが低い従業員に対して、「もう来なくていい」と感情で解雇を伝えてしまうケースも見受けられます。
しかし、労働法上は解雇には厳格なルールや手順が求められており、理由や手続きをきちんと整備していないと、不当解雇としてトラブルになりかねません。最悪の場合、解雇無効や損害賠償請求に発展し、少人数の会社にとっては大きなダメージです。
このように、採用も解雇も「就業規則」や「明確なルール」がないことで、会社側が一番リスキーな立場に立たされてしまいます。小規模だからこそ、感覚に頼らず、書面でしっかりとルールを整備しておくことが不可欠です。
小さな会社ほど“人”が命、でも離職の連鎖が…
従業員10人未満の小さな会社では、一人ひとりの存在が本当に大きな意味を持ちます。人数が少ない分、誰かが抜けるだけで会社全体の仕事の流れや雰囲気がガラッと変わってしまうほど、人は経営の命綱です。
そんな中で一度「離職の連鎖」が始まってしまうと、ダメージは想像以上に深刻です。
例えば、一人が「働き方に納得できない」「他の人の不公平感が気になる」と感じて辞めてしまうと、その理由が他の従業員にも伝わり、「自分も同じように感じていた」「今後も同じことが起きるのでは?」と不安や不信感が広がります。
さらに小さな会社ほど、業務が属人化しているケースが多く、「あの人しか知らない仕事」が必ずあります。
その人が抜けると、仕事が止まったり、お客様への対応が遅れたり、最悪の場合、取引先からの信頼も損なわれる事態に発展します。
離職のきっかけが「ルールが曖昧」「評価や待遇が不透明」など、制度の不備にある場合は、残った従業員の不満も加速しがちです。特に“家族的経営”が多い小規模企業では、「あの人だけ特別扱い」など、気持ちの行き違いから一気に空気が悪くなることもあると思います。
小さな会社ほど、「人を守る」「人を辞めさせない」仕組み=就業規則や明確なルール作りが重要です。ルールの明確化が、離職の連鎖を防ぎ、会社の命を守る土台になります。
就業規則を作るには、自分?社労士?

ここからは、実際に就業規則を作成する際に、社長が自身で作成するメリット、デメリット。労務の専門家である、社労士に依頼して作る場合のメリット、デメリットを解説します。
社長自ら作成
デメリット
社長が自分一人で就業規則を作る場合は、何より「ものすごく時間と手間がかかる」という点が最大のデメリットです。
法律の条文を調べたり、ネットで最新の情報を探したり、細かい文言を一つずつ考えたり…本業の合間にやるには、想像以上の時間と労力がかかります。
しかも、法改正が頻繁にあるため、作成しているうちに気づかないまま古い内容で進めてしまうなんてこともあるかもしれません。
ひな形を参考にしても、自社の業務や働き方に合うように直す作業が必要で、単なるコピペでは済みません。「たった数ページ」と思っていても、完成までに何度も見直しや修正が必要になり、終わりが見えないことも珍しくないです。
そのうえ、作った後も定期的な見直しや更新が必要なので、結果ずっと時間を取られることになります。本業に集中したい中小企業の社長にとっては、大きな負担になりやすいのが現実です。
メリット
一方で、社長が自分で就業規則を作るメリットもあります。
最大の利点は「自社の実態や方針に合わせてルールを細かく設計できる」ことです。
現場の業務内容や会社の文化、従業員の働き方を一番よく知っている社長自身が作ることで、使いやすく無理のない規則を作成できます。
また、一から作る過程で労務管理のポイントを深く理解でき、トラブルが起きた時も「なぜこのルールにしたか」を自信をもって説明しやすくなります。外部委託と比べてコストもかからず、従業員に直接説明する時も説得力が増します。
さらに、作成後も会社の成長や現場の声に合わせて、素早く見直しや修正がしやすいのも自作ならではの強みです。
社労士に依頼
デメリット
社労士に就業規則の作成を依頼する場合のデメリットは、まず「費用がかかる」ことです。依頼内容や会社の規模によって違いはありますが、一般的に数万円~数十万円のコストがかかります。
また、社労士は法律や労務管理のプロですが、実際の現場の細かなルールや会社ごとの独自の事情まで完全に理解してくれるとは限りません。
ヒアリングの時間や修正依頼のやり取りが必要になり、イメージと違う内容になることもあります。
さらに、外部の専門家に任せた安心感から「内容をあまり自分で確認しない」まま進めてしまうと、結局現場に合わない規則ができてしまい、後で手直しが必要になることもあります。社労士に全て丸投げではなく、必ず自社の方針や業務実態をしっかり伝えて、コミュニケーションを取りながら作成していくことが大切になります。
メリット
一方で、社労士に依頼する最大のメリットは「法律にしっかり合った正しい就業規則を効率よく作成できる」ことです。最新の法改正や行政の指導動向を把握しているため、自分で調べきれないポイントや抜け漏れを防げます。
また、これまで多くの会社の就業規則を見てきた経験から、トラブルが起きやすい部分や、現場でよくある悩みにも事前に対応した内容を盛り込んでもらえます。
手続きや提出書類の準備も一括して任せられるため、本業に集中しながらスムーズに整備が進みます。
特に初めての作成や大きな改定の時は、プロのチェックやアドバイスがあることで「安心感」も大きいです。
今後の定期的な見直しや、トラブル発生時の相談相手としても頼れる存在になるので、法令順守とリスク管理を重視する企業には非常に大きなメリットがあります。
終わりに
今回は従業員数10人未満の企業むけに、実際にきた事例も含めながら、就業規則がない場合のリスクを説明しました。
就業規則の重要度を感じていただけたでしょうか。
就業規則を作るにも方法は複数ありますし、それぞれにメリットデメリットも存在しています。
自社に合った形で就業規則を作成し、会社をリスクから守っていってください。
このほかにも、自社で最低限の最低限就業規則を整備するための記事や、変更のためのガイドになる記事も書いていますので併せて読んでみてください。
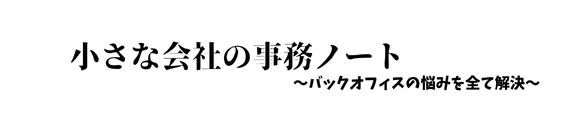
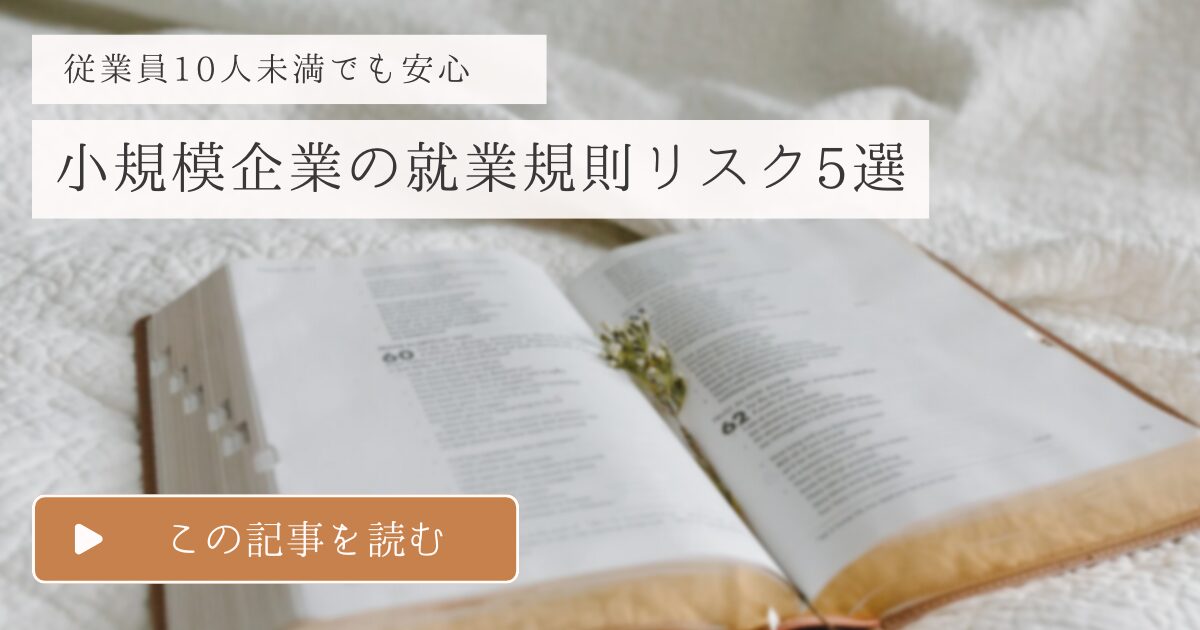

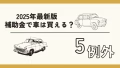
コメント