「なんとなく言われた通りにやっているけど合っているのか不安」「特に研修があったわけでもないからこれって正解かな?」「自分ではなんとなくやれているけど、次の子にどう教えたらいいかわからない」
全ての業務がマニュアル化されているわけではない、中小企業の経理ほどこのようなお悩みを抱えられていることは多いんじゃないでしょうか。
自分一人の手では回らなくなってくると当然増員は必要です。
ただ、マニュアルが無いと何を教えたらいいか分からないということが当然起こってきます。
しかし、マニュアルを一から整備するのも簡単じゃ無いですよね?
この記事では、経理に必要な基礎中の基礎知識を全て網羅しています。当然自社にあったやり方や、マニュアルを作成するのが理想ですが、そんな時間がないよと言う方は是非この記事を引継ぎの際に一度読んでもらってください。
これを読むだけで未経験の事務スタッフでも、すぐに独り立ちできる内容が網羅されています。
各項目ごとに、目的・やること・ポイントをまとめています。
また、他の記事では当然のように使われている、経理の基礎単語の解説もしています。青のボックスを読むだけでも参考になると思います。
この記事が御社の教材になるように作成しますので、これから指導する方も、新しく事務職を目指す方も、改めて知識を再確認したい方も是非参考にしてください。
経理マニュアル基礎知識一覧

1. お金の流れ・会計の全体像を見る
やること
- 会社のお金の流れ(入金・出金・残高)をざっくりつかむ
- 会計ソフトや帳簿の構成(B/S・P/Lなど)を知る
目的
会社の経営状態を数字でつかみ、日々の業務がどこにどう関係するかを理解する
ポイント
「全体像を先に知る」と、細かい処理の意味が分かりやすくなります。
経理業務を引き継ぐ際にまず重要なのはお金の流れの全貌を伝えることです。「会社のお金はどこから入ってきて、どこに出ていくのか」これを把握してもらう必要があります。
経理は「売上」や「支払い」など項目がそれぞれ細かく分かれているので、バラバラに覚えるよりも、まずお金の流れの全体像を把握することで、「この書類はなんのためのものなのか」「この入力は何を意味しているのか」が自然とイメージできるようになります。
例えば、会計ソフト上では、現金・預金・売掛金・買掛金など色々な項目が出てきますが、それぞれの項目が会社のお金のどこを表しているのかが分かると、仕訳や入力で迷うことがぐっと減ります。
また、決算書の損益計算書(P/L)は会社の儲け、貸借対照表(B/S)はお金や財産の全体像、と基本を知っておくことで、経理作業を「ただの入力作業」と感じず、会社経営を支える重要な業務として理解できるはずです。
全体像を最初につかむことが、ミスの防止や仕事のやりがいにも直結します。
2. 日々の記帳(仕訳入力)
やること
- 領収書・請求書・通帳などを集め、会計ソフトや帳簿へ記録
目的
会社のお金の出入りを、あとから見返してすぐ分かるようにしておくため
ポイント
日々の記帳(仕訳入力)は、会社の「お金の動き」をひとつずつ正確に記録する作業です。
たとえば、売上は「どこから、いくら入ったか」、仕入や経費の支払いがあれば「どこに、いくら払ったか」などを、現金や預金などの動きごとに分けて帳簿につけていきます。
この記録をしっかり残しておくことで、月末や決算時に「お金が合わない」「どこでミスをしたか分からない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。
また、正しく記帳することで、毎月の経営状況を把握できるだけでなく、税理士や社長がすぐに数字を確認することができ、資金繰りや節税の対策も立てやすくなります。
さらに、万が一税務調査が入った場合でも、きちんと帳簿をつけておけば、正しい経理をしている会社だと証明でき、会社を守ることにもつながります。
つまり、日々の記帳は会社の健康管理のような大事な仕事です。
3. 売上・請求・入金管理
やること
- 売上が発生したら請求書発行
- 入金があったら消し込み(入金記録)
目的
売上の漏れや未回収を防ぐため
ポイント
売上・請求・入金管理は、会社のお金が「きちんと入ってくるか」を管理するためにとても重要な業務です。
まず、売上が発生した時点で、商品やサービスなど何を提供したかを正確に記録します。
その後、お客様に「いつ・いくら・何の支払いをお願いするか」を明記した請求書を発行します。ここでミスがあると入金が遅れたり、トラブルの原因になるので、必ず金額・支払い期限・振込先などを正確に記載しましょう。
請求書を出した後は、実際に入金されたかどうかを通帳やネットバンキングで必ず確認します。
入金が確認できたら、会計ソフトや管理表に「〇月〇日入金済み」と記録し、未入金の場合は早めにお客様へ連絡して対応します。
売上や入金の管理がきちんとできていると、会社の資金繰りが安定し、信用も高まります。ルールやフローを作り、誰が見てもわかる管理体制を整えておくことが大切です。
4. 仕入・経費・支払管理
やること
- 仕入や経費の請求書・領収書の整理・保存
- 支払内容をリスト化し、期日ごとに支払い
目的
経費の記録漏れや支払い忘れ、不正防止のため
ポイント
仕入・経費・支払管理は、会社が何にお金を使ったのかをきちんと記録し、誰にいくら支払ったかを正確に管理するための大切な業務です。
仕入管理とは、商品や材料をどれだけ・いくらで仕入れたかを把握すること。経費管理は、交通費や消耗品、通信費など日々の仕事にかかったお金をきちんと分類し、領収書や請求書をもとにまとめることです。
支払管理では、支払先ごとに期日や金額を整理し、遅れや二重払いが起きないようにチェックします。
支払い忘れや記録ミスがあると、信用を失ったり、余計な支払いトラブルの原因にもなります。毎月の支払い予定をリストアップして、残高と照らし合わせておくことも重要です。
これらをしっかりと管理することで、会社のお金の流れが見えやすくなり、余計な出費やトラブルを防ぐことができます。結果として、資金繰りの安定や経営判断にも役立つので、日々の丁寧な記録とチェックを心がけましょう。
5. 給与計算・社会保険手続き
やること
- 勤怠データを集計し給与計算
- 税金・社会保険料の控除
- 給与明細の発行と各種保険の加入・変更手続き
目的
従業員への正確な給与支給と法令順守のため
ポイント
給与計算・社会保険手続きは、従業員に正しく給料を支払い、法律で決められた保険や税金の手続きを行う、とても重要な業務です。
給与計算では、出勤日数や残業時間、遅刻や早退、各種手当や控除(社会保険料・税金など)をもとに、1人ひとりの給料を正確に計算します。
計算ミスがあると、従業員の信頼を損ねたり、後で追加の修正やトラブルが起きやすくなります。
また、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険への加入や、退職時の資格喪失手続き、年に一度の保険料見直し(算定基礎届や労働保険の年度更新)も会社の義務です。
これらの手続きを忘れたり遅れたりすると、会社がペナルティを受けることもあります。
正確な給与計算と社会保険の手続きをして、従業員が安心して働ける環境を守ると同時に、会社を法律違反から守り、健全な経営を続けることができます。
6. 税金の基礎知識・納付管理
やること
- 消費税・法人税・源泉所得税など主な税目の把握
- 納付期限のスケジュール管理
目的
期限遅れによる罰則や延滞を防ぐため
ポイント
中小企業の経理業務でとても重要なのが、税金の知識と納付の管理です。
会社には「法人税」「消費税」「源泉所得税」など様々な税金がかかります。
税金はいつまでに、いくら払うかがきちんと法律で決まっているので、うっかり納付期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などのペナルティが発生し、余計な出費につながります。
また、給与を支払う際には源泉所得税を「天引き」してまとめて税務署に納付する必要があります。
消費税も、売上と仕入・経費で預かった金額と支払った金額を整理して、差額を納めます。
これらの計算や納付は会計ソフトで自動化できる部分も多いですが、提出先や納付期限は自社で管理する必要があります。
ポイントは、「税金の種類と納付時期」をしっかりスケジュール化し、忘れずに納付・申告を行うことです。
税理士や会計事務所と連携し、期限や金額の間違いがないようチェックしましょう。ミスや遅れを防ぐことで、会社のお金を守り、信用も高まります。
7. 決算・申告の準備
やること
- 棚卸や減価償却などの事前準備
- 決算書のドラフト作成・税理士や専門家との打合せ
目的
正確な決算・スムーズな申告のため
ポイント
決算・申告の準備は、1年間の会社の経営活動をまとめて「成績表」として正確に整理するためのとても大切な作業です。
ここでミスがあると、税金の計算が間違ったり、金融機関からの信用に悪影響が出ることもあります。
まず、売上・仕入・経費・給与など、すべての取引が帳簿に正しく記載されているか確認しましょう。
現金や預金の残高が帳簿と合っているか、売掛金や買掛金の未回収・未払いがないかもチェックします。さらに、在庫の棚卸しや、固定資産の管理、減価償却の計算も忘れずにしましょう。
決算時期は、領収書や請求書など証拠となる書類を揃えることが重要です。また、税理士や会計事務所との連携を早めにして、疑問点やミスがないかをチェックすることもポイントです。
最終的に「決算書」と「申告書」を期限内に作成・提出できれば、安心して新しい年度を迎えられます。
8. 証憑(しょうひょう)・帳簿の保存管理
やること
- 領収書・請求書・契約書などを7年間保管
- 紛失防止のための整理・データ化も推奨
目的
税務調査や会計監査など外部チェックに対応するため
ポイント
証憑(しょうひょう)とは、会社のお金の動きを証明するための書類、たとえば領収書・請求書・契約書・納品書・レシートなどのことです。
帳簿は、会社のお金の出入りをまとめて記録したノートやデータのことを指します。これらをきちんと保存・管理することは、経理業務でとても大切なポイントです。
なぜなら、税務調査などで「この支出は本当に会社のために使ったのか?」と確認されたときに、証拠として証憑や帳簿を提示する必要があるからです。
法律では、原則7年間の保存義務があり、もし失くしてしまうと経費として認められなかったり、会社にとって不利な判断をされてしまうことがあります。
保存方法も重要です。紙の場合は日付や科目ごとに分けてファイリングする、電子の場合はきちんと整理されたフォルダに保存します。定期的なバックアップも忘れずに行いましょう。
証憑や帳簿をしっかり管理することで、会社の信頼やトラブル回避にもつながります。
9. 資金繰り・現預金管理
やること
- 資金繰り表を作り、月々の入金・支払い・残高を確認
- 現金・通帳の管理、定期的な残高照合
目的
資金がショート(お金が足りなくなる事態)するのを防ぐため
ポイント
資金繰りとは、会社のお金の「出入り」をしっかり管理して、いつ・いくらお金が必要なのか、足りなくならないように調整することです。
現預金管理は、会社が持っている現金や銀行口座の残高を正確に把握し、支払い漏れや使いすぎを防ぐための業務です。
ポイントは、まず日々の現金・預金の動きを正確に記録することです。
売上の入金や支払い、銀行振込、引き出しなど、一つひとつの取引を帳簿に記載し、実際の残高と帳簿の数字が合っているかを必ず確認します。
また、これから先の入金予定・支払予定を見通し、必要なお金が足りるかどうか「資金繰り表」でチェックすることが重要です。資金ショート(お金が足りなくなること)が起きると、支払い遅延や信用低下のリスクが出てきます。
月末や期末だけでなく、日々の管理が会社経営の安定に直結します。問題が起きそうなときは、早めに対策を立てることが大切です
10. 社内規程・契約書・基本ルール
やること
- 経理規程や出張・旅費規程など、社内ルールの整備
- 取引先との契約書の保存・印紙チェック
目的
トラブル防止と法的リスク管理のため
ポイント
社内規程や契約書、基本ルールは、会社が円滑で安全に運営されるための決まりごとです。
例えば、社内規程は就業規則や経費精算ルールなど、会社内で働く人すべてが守るべきルールをまとめたものです。契約書は、会社が取引先や従業員と約束をするときにその内容を文章で残す書類です。
ポイントは、全員がどんなルールや規定が会社にあるのかを知っておくことです。
例えば、どんな時にどのハンコが必要なのか、経費はいくらまでなら社長の承認がいるか、などを明確にしておくと、あとから言った・言わないのトラブルになるのを防げます。
また、契約書は必ず内容を確認し、会社にとって不利な条件がないか、法律に違反していないかもチェックが必要です。トラブルが起きた時も、きちんとした書面があれば会社を守る証拠になります。
これらのルールや書類は、定期的に見直し・保存を徹底し、引き継ぎ時にも何がどこにあるかを整理しておくことが、安心できる経理・総務業務の土台となります。
このルールの見直しに関しては、会社全体に大きく関わる内容なので、社長との細かな相談が必須です。
終わりに
今回はマニュアル作りを意識しながら書いてみましたがいかがでしょうか。
ここに書かれた内容は、どの企業でも当てはまるような汎用的なものばかりです。会社や業種によって独自のルールも存在していると思います。
この記事を初歩の初歩として、会社ごとにブラッシュアップしてもらえると嬉しいです。
またこのほかにも、ミスを減らすためのシステム化に関する記事や、おすすめの資格、最後に登場した就業規則に関する記事も作成しています。併せて読んでもいただけると幸いです。
【保存版】事務作業が3時間減る!無料で使える時短ツール5選(会計・勤怠・連絡)
経理資格おすすめ3選|難易度と活用法を徹底解説
【社長の奥さん向け】就業規則が必要な3つの理由と「最低限だけ」作るテンプレ
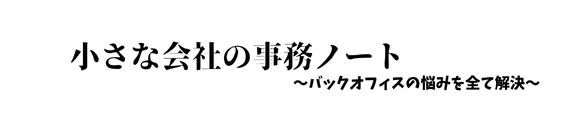
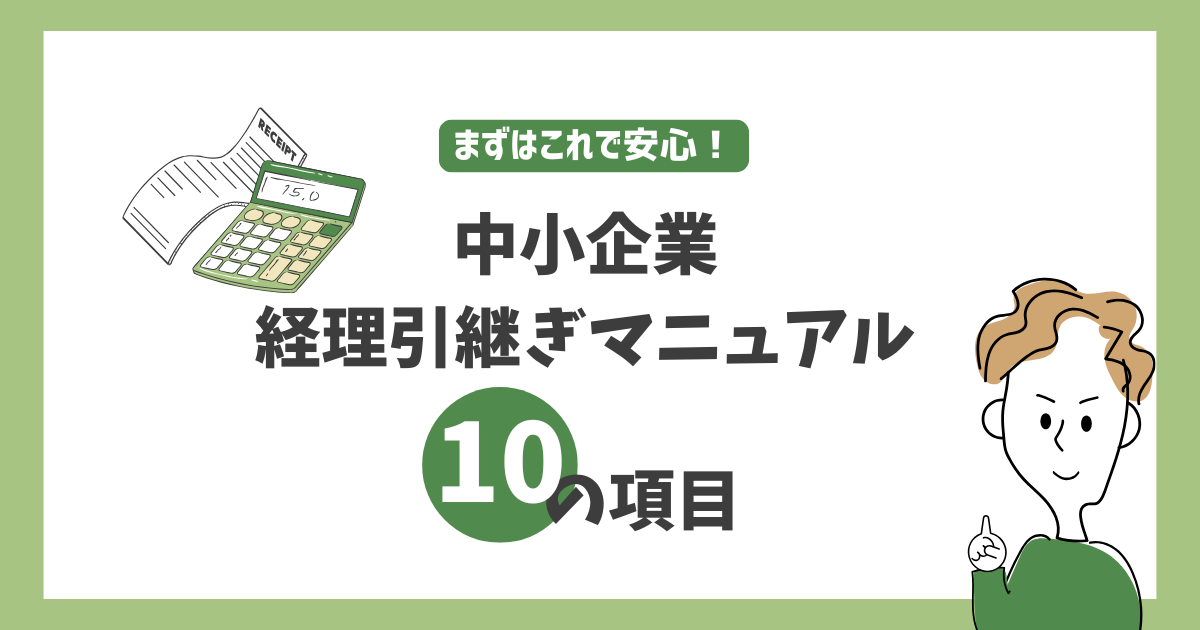


コメント